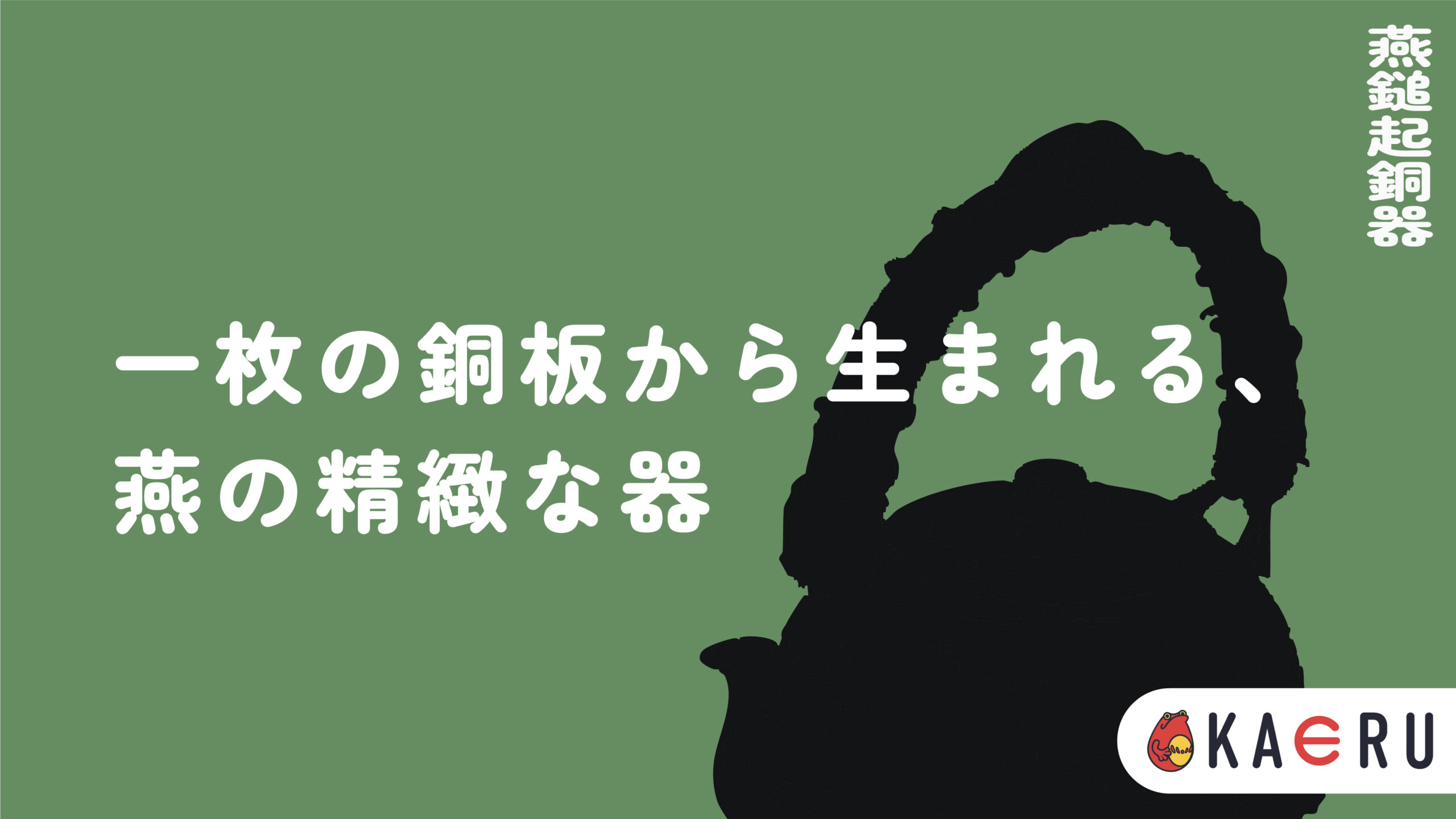燕鎚起銅器とは?
燕鎚起銅器(つばめついきどうき)は、新潟県燕市で作られている伝統的工芸品で、1枚の銅板を金槌で打ち起こして器の形を成形する「鎚起(ついき)」という技法によって製作されます。やかん、急須、鍋などの実用品から、花瓶やワインクーラーといった美術工芸品に至るまで、多様な製品がこの技術によって生み出されてきました。
表面には、化学反応による伝統的な着色が施され、使い込むごとに美しい光沢が深まり、経年変化を楽しむことができます。数百種類に及ぶ金鎚や当て金を使い分けて成形される燕鎚起銅器は、機械では決して再現できない人の手仕事の結晶です。
| 品目名 | 燕鎚起銅器(つばめついきどうき) |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 分類 | 金工品 |
| 指定年月日 | 1981(昭和56)年6月22日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(27)名 |
| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

燕鎚起銅器の産地
世界に誇る金属加工のまち「燕」

主要製造地域
燕鎚起銅器の主産地である新潟県燕市は、信濃川の流域に広がる越後平野の中央部に位置し、隣接する三条市とともに「燕三条」として金属加工の一大産地として知られています。この地域では、古くから信濃川の氾濫と向き合いながら、農閑期の副業として発展した鍛冶仕事が、やがて金属加工産業へと発展。現在では、洋食器・刃物・工具・銅器など、金属製品の多様な製造が行われており、全国生産の多くを占めています。
燕市の町には金属加工業を営む町工場が密集し、職人の手技が連綿と受け継がれていることが、燕鎚起銅器の高い品質と技術力を支えています。
燕鎚起銅器の歴史
和釘から銅器へ、燕の町に刻まれた金属加工の系譜
燕鎚起銅器の歴史は、農業に適さない厳しい環境と向き合いながら、生活を支える副業として金属加工が発展してきた背景に根差しています。
- 1626年(寛永3年):代官が農民救済のため、江戸から和釘職人を招き、鍛冶技術の導入が始まる。
- 1681〜1683年(天和年間):燕地域で和釘製造に従事する鍛冶職人が1000人を超えたと伝えられる。
- 1697年(元禄10年):江戸の大火により復興需要が高まり、燕の和釘が舟で江戸へ輸送される。
- 1650年頃(慶安期):村上藩の命により、神社の装飾金具や銅細工の製作が始まる。
- 1764〜1771年(明和年間):仙台の職人・藤七が鎚起技術を燕に伝え、銅器生産が本格化。
- 1830年代(天保年間):近隣の間瀬銅山で良質な銅が採掘され、地場産業としての基盤が強化。
- 1870年代(明治時代初期):西洋への輸出拡大のため彫金技術が導入され、芸術性が高まる。
- 1894年(明治27年):明治天皇への献上品として花瓶が選ばれ、燕鎚起銅器の技術力が評価される。
- 1981年(昭和56年):燕鎚起銅器が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
こうした長い歴史の中で、燕鎚起銅器は日用品から芸術品へと進化を遂げてきました。
燕鎚起銅器の特徴
金槌と銅が響き合い、時とともに育つ器
燕鎚起銅器の魅力は、なんといってもその「継ぎ目のない美しさ」にあります。一枚の銅板を金槌で丹念に打ち出していくことで、注ぎ口も取っ手も一体となった器が完成します。特に、そそぎ口までも一枚の板から打ち出す「口打出(くちうちだし)」と呼ばれる技術は、限られた熟練職人にしかできない高度な技であり、燕鎚起銅器の象徴ともいえる存在です。
器の形状を作る際には、約200種類の金槌と300種類を超える当て金を使い分けます。これは形状ごとに最適な道具を選ぶことで、繊細で美しい曲面や稜線を表現するため。道具を知り、金属の性質を読み、力の加減を見極めることこそが、職人に求められる最も高度な技術とされています。
さらに、表面の仕上げにも奥深い工夫が施されています。たとえば着色には、緑青(ろくしょう)や硫酸銅といった薬品を使い、銅器を煮込むことで化学反応を起こして発色させます。この“煮る”工程により、赤銅色や黒銅色などの深みある色調が生まれ、作品に格調を与えています。気温や時間、薬液の濃度によって発色が変わるため、同じものは二つと存在しません。
燕鎚起銅器は「使いながら育てる器」です。銅は使い込むほどに表面に艶が増し、時間とともに味わい深い風合いへと変化します。この経年美化こそが、金属工芸の本質であり、所有者とともに時を刻む道具としての価値を高めています。
燕鎚起銅器の材料と道具
300種を超える当て金が支える、職人の自由な造形
燕鎚起銅器の製作には、非常に多くの専用道具と高品質な素材が用いられます。特に、金槌と当て金は職人にとって命ともいえる存在です。
燕鎚起銅器の主な材料類
- 銅板:現在は主にチリやボリビアから輸入した高純度の銅を使用
- 緑青・硫酸銅:化学反応による伝統的な着色に用いる薬品
- 木炭:加熱時の熱源(かつては下田郷産)
燕鎚起銅器の主な道具類
- 金槌:約200種類におよぶさまざまな大きさ・形の槌
- 当て金:約300種類以上。成形する形に応じて使い分ける
- 火炉:焼きなましの際に使用
- 彫金用たがね:模様を刻むための専用工具
これらの素材と道具の組み合わせにより、唯一無二の銅器が生み出されています。
燕鎚起銅器の製作工程
熱と打撃で命を宿す、伝統の銅器づくり
燕鎚起銅器の製作は、複数の工程を何度も往復しながら、ひとつの器を丁寧に仕上げていきます。
- 地金とり・打ち起こし
銅板を製品サイズに切り出し、木台の上で木槌を使って打ち起こし、基本の形を作る。 - 打ちしぼり
当て金に銅板をあて、金槌で打ち縮めて立体形状にする。熟練の感覚で徐々に側面が立ち上がっていく。 - 焼きなまし
叩いて硬くなった銅を650℃程度で加熱し、水で冷却して再び柔らかくする。成形との間に何度も繰り返す。 - 成形
曲線のバランスや厚みを整えながら、全体を均等に仕上げていく。 - 彫金
たがねと小槌で細かな模様を打ち出す。装飾性を高め、独自性を付与する重要な工程。 - 着色・磨き
緑青と硫酸銅を混ぜた液で煮込む。時間・温度・濃度の調整によって、さまざまな発色が得られる。 - つる(取っ手)の取り付け
最後に持ち手や注ぎ口などを取り付け、製品として完成させる。
こうした器を生み出すには、長年にわたる修業が必要とされます。弟子入りから完全に一人前の職人として独り立ちするまでには、通常6年から10年を要すると言われており、その道のりはまさに一打ごとの積み重ねです。目や耳、指先で金属の変化を感じ取りながら、道具と対話し、技を自分のものとしていく年月が、燕鎚起銅器の奥深さを支えているのです。