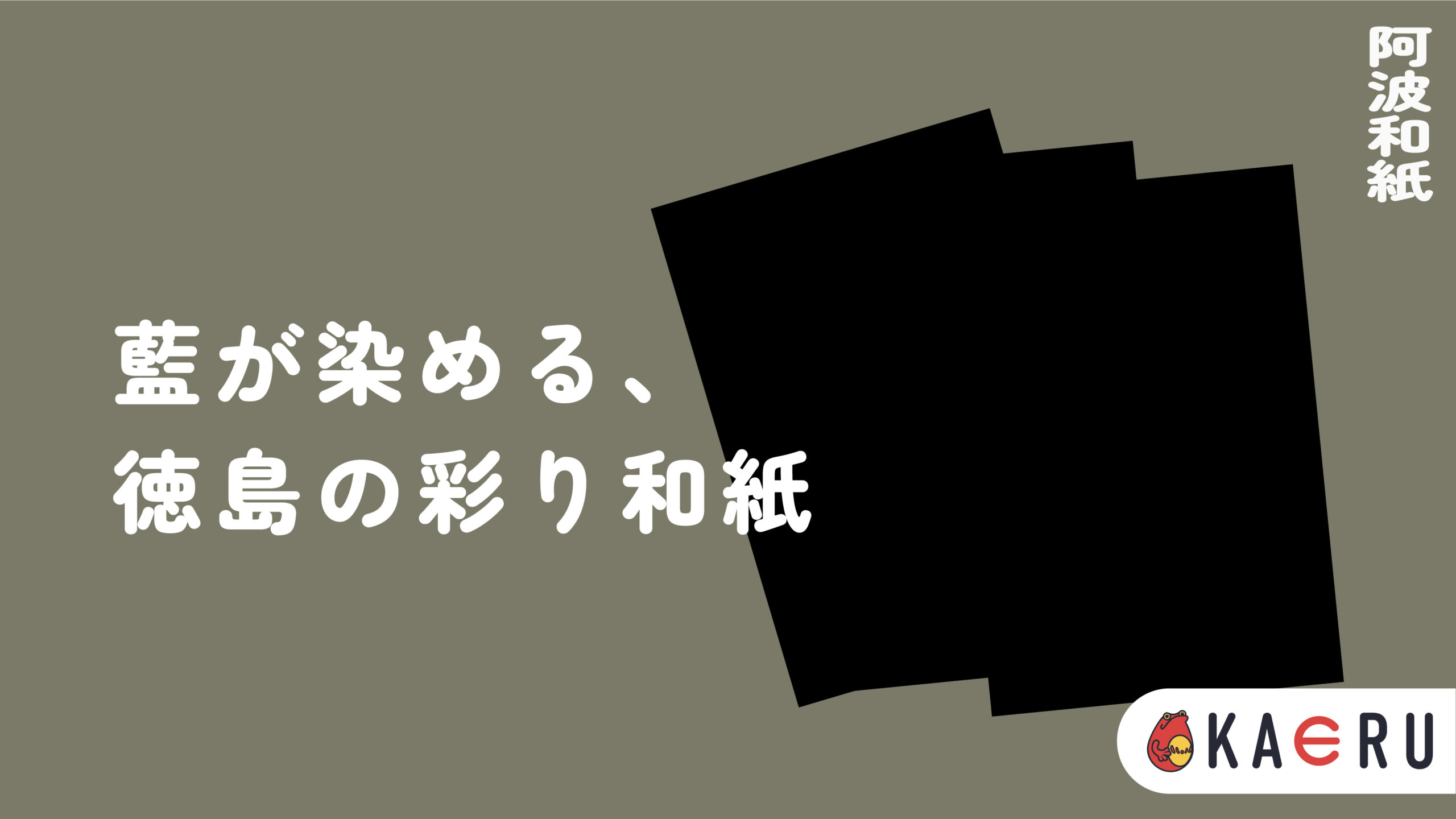阿波和紙とは?

阿波和紙(あわわし)は、徳島県吉野川市や那賀町、三好市を中心に作られている伝統的な手漉き和紙です。その起源は奈良時代にさかのぼり、1300年以上にわたって受け継がれてきました。
この和紙の最大の特徴は、破れにくく水にも強いという実用性と、しなやかで柔らかな質感、そして豊かな色彩と模様による表現力にあります。特に「藍染め和紙」や「もみ染め」「しぼり染め」といった創意工夫に富んだ染色技法は、他産地の和紙とは一線を画す個性を放ちます。
伝統を守りながらも現代ニーズに応え、印刷適性に優れた機械漉き和紙や、インテリア用の壁紙・包装紙なども開発。阿波和紙は今なお進化を続ける“紙の芸術”なのです。
| 品目名 | 阿波和紙(あわわし) |
| 都道府県 | 徳島県 |
| 分類 | 和紙 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 5(16)名 |
| その他の徳島県の伝統的工芸品 | 阿波正藍しじら織、大谷焼(全3品目) |

阿波和紙の産地
水と藍と文化が織りなす、紙づくりの風土

主要製造地域
阿波和紙の主な産地である吉野川市、那賀町、三好市は、いずれも徳島県の自然豊かな地域に位置します。紙づくりに不可欠な「水」「植物」「気候」「文化」が理想的に揃った地であり、その風土が阿波和紙の品質と個性を育んできました。忌部族がこの地に定住して以来、和紙づくりの技術が脈々と受け継がれてきました。中世以降は徳島藩の保護政策や藍栽培の推進により、和紙産業が地域経済の一角を担うまでに成長。町や農村部には紙漉き場が点在し、紙を媒介にした地域のつながりも形成されていきました。
また、藍染めの本場・徳島ならではの審美眼と工芸的な感性が、和紙の染色や模様に豊かに表れています。伝統的な「そめ紙」は、単なる実用品ではなく、贈答や芸術作品としても重宝されました。
四国山地を水源とする那賀川・吉野川の清流は紙漉きに適した軟水を供給し、年間を通して温暖湿潤な気候が繊維の扱いや乾燥にも好影響をもたらします。加えて、山間地に育つ楮・三椏といった原料植物が自給できる地の利も大きく、徳島はまさに和紙づくりの「自然工房」と言えるでしょう。
阿波和紙の歴史
1300年を刻む、紙とともにある暮らしの足跡
阿波和紙の歴史は、奈良時代にまでさかのぼります。製紙の祖とされる忌部(いんべ)族がこの地に定住し、楮や麻を植えて紙や布を作ったのが始まりとされます。以来、地域の生活と密接に関わりながら、阿波和紙は進化を遂げてきました。
- 8世紀初頭(奈良時代): 忌部族が阿波に入り、麻や楮を用いた製紙・製織の技術を伝える。朝廷への貢納紙として用いられる。
- 13世紀(鎌倉時代): 修験道や寺社の写経紙として使用され、品質の高さが評価されはじめる。
- 17世紀(江戸時代前期): 徳島藩が藩内産業として紙漉きを奨励。紙の専売制度を導入し、流通が整備される。
- 18世紀(江戸時代中期): 藍染め和紙が誕生。藍の副産物として紙染め技術が開花し、多様な模様染めが登場。
- 19世紀初頭(江戸時代後期): 「そめ紙」が贈答用・装飾用として京阪神でも人気を集める。
- 1870年代(明治初期): 機械漉き技術が一部導入され、手漉き和紙との棲み分けが進む。
- 1930年代(昭和戦前期): 印刷用途への展開が始まり、文芸誌や美術書に採用される。
- 1976年(昭和51年): 阿波和紙が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代: インテリア・アート・文具といった多分野へ展開し、海外からの評価も高まる。
このように、阿波和紙は自然・技術・文化が織りなす歴史の結晶として、今もなお人々の暮らしに彩りを添え続けています。
阿波和紙の特徴
紙の中に、色と物語を織り込む技
阿波和紙の魅力は、ただの「白い紙」では終わらないところにあります。たとえば藍染め和紙は、見る角度や光の当たり方で表情が変わる独特の深みがあり、「紙の中に青が生きている」とも称されます。これは徳島産の天然藍を使った伝統的な染色技法によるもので、ほかの産地ではなかなか見られないものです。
さらに、手で紙をもみながら染料を加える「もみ染め」では、偶然性を活かした模様が現れ、二つと同じ柄は生まれません。「しぼり染め」では、絞った跡が花火のように広がり、紙の上に自然の力が刻まれたかのような美しさがあります。
また、阿波和紙は実用品としての強さも兼ね備えており、水に濡れても破れにくく、筆あたりも柔らかいことから、書道や版画、製本用としても根強い支持を集めています。最近ではプリンター対応の和紙や、香り付きの和紙、LED照明と組み合わせた照明器具など、新たな表現の可能性も切り拓かれています。

阿波和紙の材料と道具
自然素材と手技が響きあう、紙づくりの礎
阿波和紙の製作には、地元で育まれた植物原料と、水・火・道具を用いた繊細な工程が不可欠です。
阿波和紙の主な材料類
- 楮(こうぞ):繊維が長く、強度・柔軟性に優れる主原料。
- 三椏(みつまた):なめらかな質感を生み出す。主に書画用紙や美術用途に使用。
- 藍(あい):徳島産の天然藍を用い、紙に深みのある色を染め上げる。
- 染料・顔料:紅・黄・紫など自然由来の色材も使用される。
阿波和紙の主な道具類
- 桁(けた):漉き枠。和紙のサイズや厚みを左右する。
- 簀(す):竹製のすだれ状道具。繊維を均一に配する。
- ねり:トロロアオイの根から得る粘剤。繊維を分散させる。
- 桶・槽(おけ・ふね):繊維と水を混ぜて紙を漉くための容器。
素材と道具を熟知し、絶妙な加減で漉き上げる職人の勘こそが、阿波和紙の芸術性を支えているのです。
阿波和紙の製作工程
手で漉き、目で確かめ、紙を育てる
阿波和紙の製作工程は、約20にも及ぶ手作業の積み重ねからなります。
- 原料処理
楮の皮を剥ぎ、煮沸して不純物を取り除く。漂白・叩解して繊維をほぐす。 - ねりづくり
トロロアオイの根から粘剤を抽出。繊維の流動性を調整。 - 漉き(すき)
桶に原料とねりを入れ、簀桁で紙を一枚ずつ漉く。 - 脱水・圧搾
漉いた紙を積み重ね、加圧して水分を除く。 - 乾燥
天日または乾燥板で乾かす。平滑性や色調を整える重要な工程。 - 仕上げ
必要に応じて染色・模様づけを施す。断裁や検品もここで行う。
こうして出来上がる阿波和紙は、一枚一枚が自然と人の技の結晶です。見た目の美しさだけでなく、紙としての強さや機能美も兼ね備えた逸品として、国内外で高く評価されています。
1300年の歴史を持つ阿波和紙は、紙という素材に色彩や物語を織り込んできた徳島の誇る伝統工芸です。藍やもみ染めの美しさと、丈夫さ・実用性を兼ね備えたその和紙は、現代の暮らしにも息づき続けています。