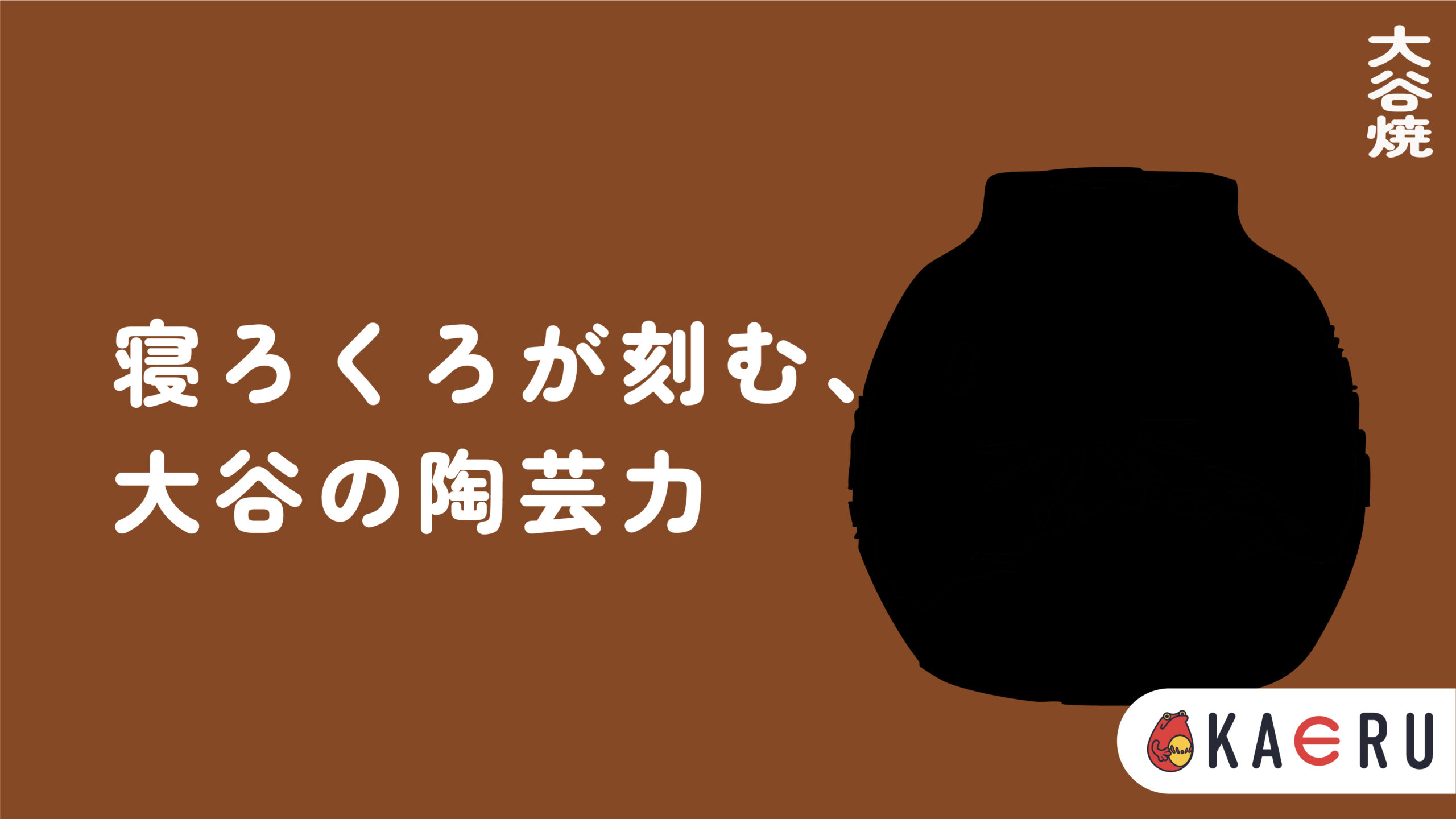大谷焼とは?

大谷焼(おおたにやき)は、徳島県鳴門市大麻町大谷を中心に作られている陶器で、江戸時代後期から240年以上の歴史を持つ伝統工芸です。藍染に使う大型のかめの生産から発展し、独自の技法「寝ろくろ」で知られています。
職人が寝そべりながら足でろくろを回し、もう一人が成形を行うこの技法は、日本の陶芸の中でも極めて珍しく、大谷焼ならではの大物陶器づくりを支えています。現在では、水がめや藍がめのほか、マグカップ・皿・花器などの日用品・インテリア陶器へと展開し、重厚な中にも優しさを感じさせる焼き物として注目を集めています。
| 品目名 | 大谷焼(おおたにやき) |
| 都道府県 | 徳島県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 2003(平成15)年9月10日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 9(9)名 |
| その他の徳島県の伝統的工芸品 | 阿波正藍しじら織、阿波和紙(全3品目) |

大谷焼の産地
藍と土と信仰が息づく、陶芸の里・鳴門大麻町
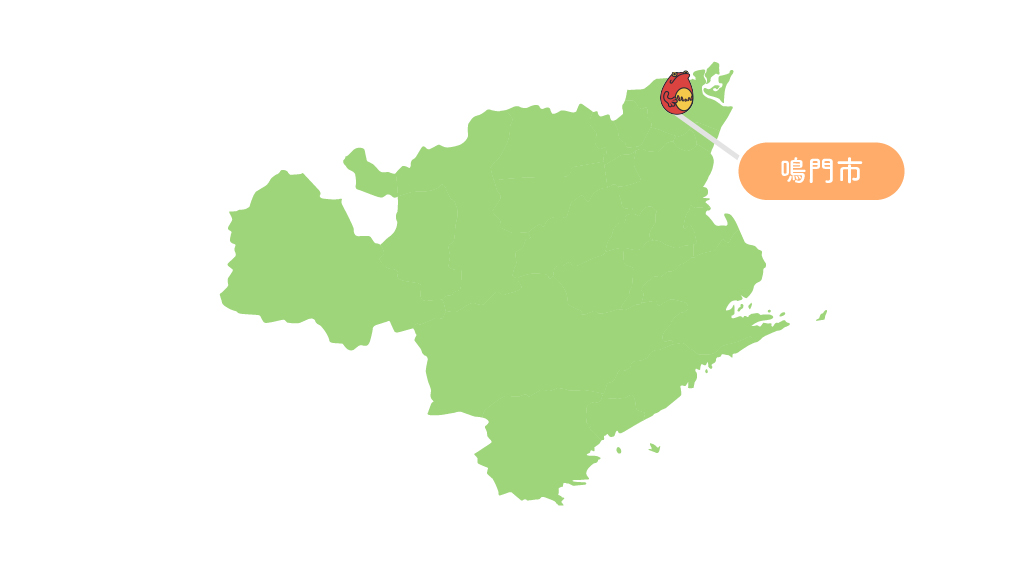
主要製造地域
大谷焼の産地である徳島県鳴門市大麻町大谷は、藍染文化と深く結びついた地であり、地理・文化・気候の三面から陶芸に適した条件が揃っています。江戸時代から阿波藍の一大生産地として栄え、藍を発酵・熟成させるための「藍がめ」の需要が高まり、大物陶器の産地として発展しました。また、四国八十八箇所霊場の第一番札所・霊山寺や、大麻比古神社の門前町として多くの遍路や参拝者が訪れる地域であり、外部からの技術や文化が流入しやすい土壌がありました。1780年代の創窯も、こうした人的往来が契機となっています。
また、阿波藍の製造や流通を支えた豪農・豪商の存在が陶器文化の普及に貢献しました。特に納田家のように外部から職人を招いて技術導入を図った例があり、大谷焼は“地場の土を使った実用品”でありながら、技術的には近隣他県の陶芸文化とも交差しています。近年は作家による芸術作品も生まれ、伝統と革新の融合が見られます。
さらに、瀬戸内海式気候の穏やかな晴天が続く気象条件のもとで、長期間の自然乾燥が可能です。特に大物陶器は乾燥に数週間を要するため、急激な湿度変化が少ないこの地域の気候は理想的です。また、登り窯の焼成には薪の確保が重要ですが、山林資源が周辺に豊富にあったことも焼き物の継続的な生産を支えてきました。
大谷焼の歴史
お遍路が運んだ技と、藍が育てた焼き物の系譜
大谷焼は、江戸時代後期、徳島の地にお遍路で訪れた細工師から始まったとされています。その後、信楽から職人を招いたことで技術が本格化し、登り窯を築いて大物陶器の一大産地へと成長しました。
- 1780年(安永9年):大麻比古神社を訪れたお遍路の焼き物細工師が、大谷の赤土を使い即席で焼き物を披露。地元の人々に強い印象を残す。
- 1781年(天明元年):地元の豪農・納田平次兵衛が焼き物の将来性を見出し、信楽焼の職人を招いて技術導入を図る。
- 1784年(天明4年):登り窯を大谷村に築窯。大物陶器の本格的な製造が始まる。藍の発酵用「藍がめ」が主力製品として定着。
- 1830年代(天保年間):阿波藍の最盛期を迎え、藍がめの大量需要により大谷焼が飛躍的に発展。藩内外へ流通が広がる。
- 1870年以降(明治時代):化学染料の登場により藍染需要が減少し、かめの生産が減少するも、家庭用雑器・植木鉢などの製品へと転換。
- 大正〜昭和初期:登り窯による焼成が続けられ、大谷焼の技術が地域に定着。大型品の需要は引き続き健在。
- 1960年代:高度経済成長期に伴い、日用品の大量生産が主流となるなかで大谷焼の生産量が一時落ち込む。
- 1980年代以降:生活雑貨やオブジェ、芸術作品としての大谷焼の再評価が進み、作家活動も活発化。
- 2003年(平成15年):大谷焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」として指定される。
- 現代:観光と教育を融合させた窯元巡りや体験型ワークショップが盛んに行われ、地域資源としての大谷焼が注目を集めている。
大谷焼の特徴
重さと温かさを併せ持つ、唯一無二の“大物感”
大谷焼の最大の魅力は、やはり「寝ろくろ」を用いた大物陶器の存在感にあります。職人二人がかりで成形されるかめや壺は、人の身体ほどのサイズにもおよび、重さは100kgを超えることもあります。通常のろくろ作業では不可能なスケール感が、大谷焼ならではの風格を生み出しています。
使われる土は鉄分を多く含み、焼成後は焦げ茶や灰色、銀色といった深みのある渋い色合いに。近づいて見ると細かい凹凸があり、手触りには土本来のぬくもりが感じられます。素焼きを経ずに釉薬を施す「生がけ」の技法により、釉薬の流れやムラがそのまま景色となり、ひとつひとつ異なる表情を持ちます。
大谷焼の登り窯が「日本最大級の規模」を誇る点も見逃せません。約50mもの傾斜を持つ巨大窯で、5〜6日間昼夜を分かたず薪を焚べ続けることで、重厚な焼き締まりと艶やかな表面を実現しています。
また、現代の作家によるマグカップや皿にも、大谷焼の土の表情や釉の流れが息づいており、使うごとに愛着が深まる“育てる器”として人気です。

大谷焼の材料と道具
鉄分豊かな土と、人の呼吸でまわるろくろ
大谷焼の製作では、地元で採れる重厚な粘土と、大物成形に適した伝統工具が用いられています。粘土の性質とろくろの扱いが、焼き物の表情を大きく左右します。
大谷焼の主な材料類
- 萩原粘土(はぎわらねんど):地元産の赤土を含む陶土。焼成後に焦げ茶色の色合い。
- 讃岐粘土・姫田粘土:鉄分を多く含み、金属光沢をもつ焼き上がりに。
- 釉薬:生がけ技法により、素焼きをせず直接掛けられる透明・灰釉など。
大谷焼の主な道具類
- 寝ろくろ:一人が寝転び足で蹴って回す、二人一組の大型成形用ろくろ。
- へら・こて:成形の際に形を整えるための道具。
- 桶・バケツ:釉掛けのための道具類。
- 窯道具(棚板・支柱など):登り窯やガス窯での焼成時に使用。
寝ろくろを使った成形は、息を合わせた二人作業でのみ可能な技。土と人が一体となる、伝統技術の粋を感じさせます。
大谷焼の製作工程
二人一組で挑む、重力と火の対話
大谷焼の製作は、大物陶器ゆえの重厚なプロセスを経て完成します。一つのかめを作るには、数週間から1ヶ月以上の工程が必要です。
- 成形
地元の粘土をこねて塊にし、寝ろくろで成形。職人一人が足で蹴って回転を維持し、もう一人が手で形を整える。大物ほど熟練の技と呼吸の一致が必要。 - 施釉(せゆう)
素焼きをせず、湿った素地に釉薬をかける「生がけ」で施釉する。自然な流れや溜まりが、模様のように焼き上がる。 - 乾燥
室内で約20日間、さらに屋外で2〜3日をかけてじっくり乾燥。ひび割れを防ぎ、均等な水分蒸発が重要となる。 - 焼成
登り窯では薪を使い、1230度の高温で5〜6昼夜かけて焼き上げる。近年はガス窯も併用し、効率化を図りつつ、作品に応じた焼成方法が選ばれる。
大谷焼は、重力・炎・粘土との対話を重ねて初めて形をなす陶器です。成形から焼成まで一貫して手作業で行われるその器には、伝統の技と職人の魂が宿っています。
大谷焼は、阿波藍文化の発展とともに生まれた、徳島が誇る大物陶器です。寝ろくろによる人の技と、土の力を最大限に引き出す伝統技法によって、一つひとつの器に重厚な個性が宿ります。暮らしに寄り添いながら、観る者の心を動かす美しさを持つ、まさに“用の美”を体現した工芸品です。