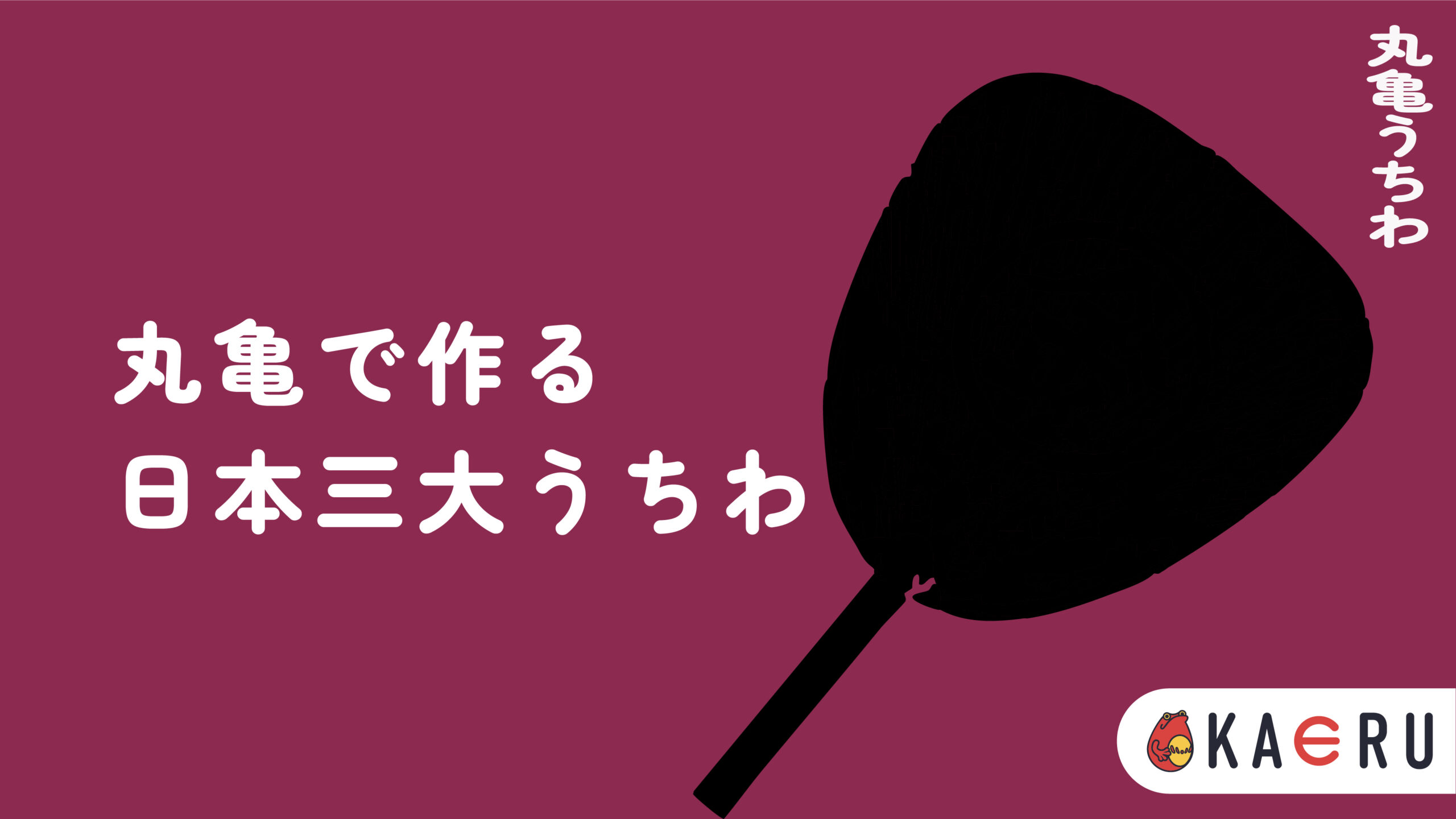丸亀うちわとは?

丸亀うちわ(まるがめうちわ)は、香川県丸亀市で生産される伝統的な手工芸うちわです。一本の竹から骨と柄(え)を作り出し、和紙を貼って仕上げるその技法は、江戸時代から続く職人の技の結晶です。その魅力は、用途に応じた多彩な形状や意匠にあります。涼をとるだけでなく、料理を冷ましたり、火を起こしたり、また装いや贈答品としても重宝され、日常の様々な場面に寄り添ってきました。
房州うちわ・京うちわと並ぶ「日本三大うちわ」のひとつでありながら、丸亀市は全国の約90%のうちわを生産する日本一の産地でもあります。
| 品目名 | 丸亀うちわ(まるがめうちわ) |
| 都道府県 | 香川県 |
| 分類 | その他の工芸品 |
| 指定年月日 | 1997(平成9)年5月14日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 9(9)名 |
| その他の香川県の伝統的工芸品 | 香川漆器(全2品目) |

丸亀うちわの産地
海と信仰、温暖な気候が支えたうちわの都

主要製造地域
丸亀うちわの産地である香川県丸亀市は、瀬戸内海に面した港町で、古くから海運と商業の要衝として栄えてきました。とりわけ江戸時代には、全国から多くの人々が「こんぴら参り」に訪れ、その参拝客を迎える港町として賑わいました。丸亀の港では人と物が頻繁に行き交い、名物として販売された「うちわ」は、旅の記念や土産物として全国へと持ち帰られ、その名が広まりました。
また、丸亀藩では藩士の副業としてうちわ製造を奨励。これにより職人が増え、製造技術が洗練される土壌が整っていきます。さらに、竹は伊予(愛媛県)、紙は土佐(高知県)、のりは阿波(徳島県)と、四国全域から高品質な素材が揃う地理的利便性がありました。このような地域間連携のもと、「讃岐うちわ」は四国を代表する地場産業へと成長していきます。
気候の面でも、温暖で湿気の多い瀬戸内気候は、風を送る道具としてのうちわの需要を支えました。電気のなかった時代、家の中に風を取り入れるためにうちわは欠かせない生活道具であり、その消費の多さが産業の継続性につながりました。こうして、丸亀は「うちわの都」としての地位を確立していったのです。
丸亀うちわの歴史
金毘羅信仰が生んだ、手仕事の伝統
丸亀うちわは、江戸時代初期から現代まで、信仰と商業、暮らしと共に歩んできた伝統工芸です。
- 1600年代初頭(江戸初期):金毘羅大権現への参拝が盛んになり、参道や港町では土産物として「丸金印入りうちわ」が販売されはじめる。
- 1670年代:丸亀藩が藩士の内職としてうちわ製造を奨励。町人や女性の仕事としても広がる。
- 1750年代:地域内に専門の職人が定着し、意匠や骨数の多様化が進む。
- 1880年代(明治20年代):鉄道や海運で販路が広がり、全国各地から注文が寄せられる産業へ成長。
- 大正時代:うちわの意匠に印刷技術が導入され、広告うちわ・装飾うちわとしての需要が増加。
- 1960年代(昭和40年代):扇風機・クーラーの普及により需要が減少。手仕事のうちわは高級品や贈答用へと転換。
- 1997年(平成9年):丸亀うちわが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:全国シェア90%を維持。技術講座や若手職人育成が進み、生活用品から芸術品まで多様な展開が進んでいる。
時代に合わせて役割を変えながらも、生活道具・贈答品・観光資源として息づき続ける工芸です。
丸亀うちわの特徴
機能と美を両立した、暮らしに寄り添う道具
丸亀うちわの最大の特徴は、一本の竹から柄と骨を一体で削り出す構造にあります。強度と柔軟性を両立させるこの技法は、見た目の美しさだけでなく、軽やかな使い心地も生み出します。
うちわの形状や柄のバリエーションが非常に豊富で、約200種を超えると言われるほど。風を送るためだけでなく、料理を冷ましたり、火を起こしたり、日除けや虫除け、浴衣に合わせたおしゃれ用の小物など、目的に応じた使い方に合わせて形やデザインが工夫されてきました。これにより、「暮らしの道具」としての普及力を高めてきたのです。
また、紙と竹の接合部である「へり」や「みみ」などの細部には、装飾性と補強の工夫が凝らされており、外見だけでなく耐久性の高さも評価されています。軽さ・丈夫さ・見た目の華やかさを兼ね備えたこのうちわは、現代でも海外へのお土産やインテリアとして人気です。
丸亀うちわの材料と道具
四国が育む、涼の素材と手の技
丸亀うちわは、四国各地の自然素材と、それを巧みに操る道具によって作られます。素材の選定から道具の使いこなしまで、熟練の感覚が求められます。
丸亀うちわの主な材料類
- 伊予竹(愛媛県産):細身でしなやか。骨と柄を一本の竹から作る。
- 土佐和紙(高知県産):通気性と強度に優れ、貼りやすい。
- 阿波のり(徳島県産):和紙貼り用の接着材として使用。
- へり紙・みみ紙:周縁を補強し意匠性を高める細長い紙材。
丸亀うちわの主な道具類
- 小刀:柄や骨の成形・削り出しに使用。
- キリ:節に穴を開ける道具。
- 型がま・木槌:紙貼り後に余白を裁断する成形具。
- 糸・針:骨組みの安定のために使用。
こうした素材と道具を使いこなすことで、実用性と装飾性を両立したうちわが生まれます。
丸亀うちわの製作工程
技でつむぐ、涼の工芸
丸亀うちわには、実に約40もの工程が存在します。ここでは代表的な平柄うちわの製作工程をご紹介します。
- 木どり
長さ40〜45cmに竹を切り、柄の幅に割る。 - 割き
柄部分から10cm程度を細かく35〜45本に裂く。 - もみ・穴あけ
繊維に沿って骨を柔らかくし、節に弓竹を通す穴を開ける。 - 柄けずり・装飾
小刀で柄を整形。装飾を施す場合もある。 - 編み
弓竹を通し、糸で骨を編み、全体を左右対称に整える。 - 貼立・型切り
骨にのりを塗り、両面に和紙を貼って木槌で成形。 - へりとり
ふちにへり紙、弓竹端にみみ紙を貼り、完成。
丸亀うちわは、一本の竹に始まり、多くの工程を経て生まれる涼の工芸品です。暮らしの中に溶け込みながらも、信仰・地域資源・職人技が織りなす奥深い背景を持つ存在として、今も人々に愛され続けています。