博多織とは?

博多織(はかたおり)は、福岡県福岡市を中心に生産される先染めの絹織物で、特に着物の帯として知られる日本有数の伝統工芸品です。その最大の特徴は、無数の細い経糸に対し、数本の緯糸を束ねた太い糸を打ち込むことで生まれる厚みと締め心地の良さにあります。しっかりと打ち込まれた絹糸同士が擦れ合うと「キュッ」と鳴る、通称「絹鳴り」と呼ばれる音は、博多織の品質を象徴する音色です。
武士にも愛され、江戸時代には将軍家への献上品に選ばれた博多織は、粋を重んじる文化と結びつきながら、800年にわたり受け継がれてきました。現在も高級帯の代名詞として広く用いられ、近年ではバッグやネクタイ、名刺入れなど、現代のライフスタイルにも調和する製品展開が進んでいます。
| 品目名 | 博多織(はかたおり) |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月14日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 55(117)名 |
| その他の福岡県の伝統的工芸品 | 久留米絣、小石原焼、上野焼、八女福島仏壇、博多人形、八女提灯(全7品目) |
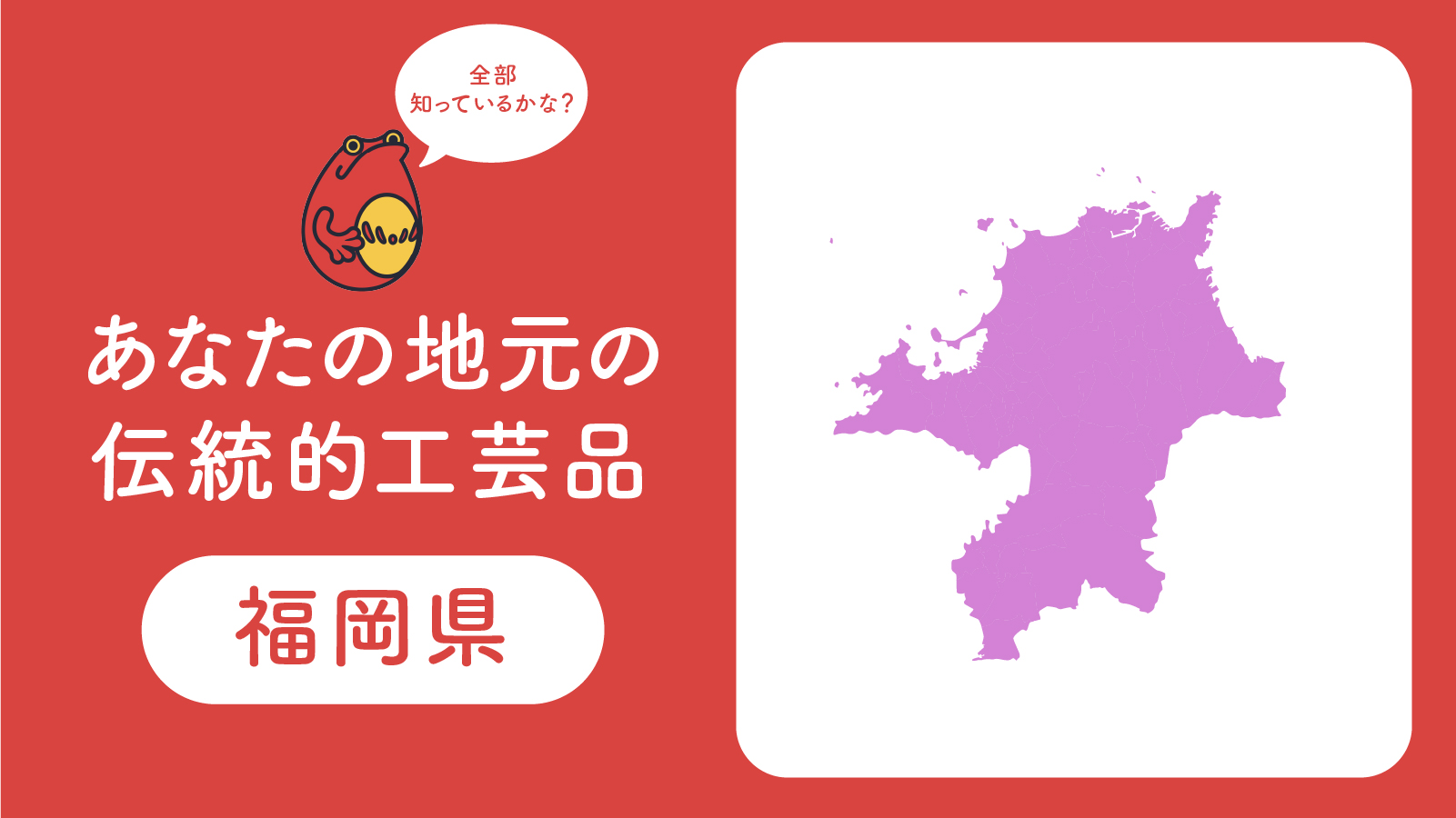
博多織の産地
交易・信仰・気候が織りなす、織物文化のるつぼ

主要製造地域
博多織の主産地である福岡市博多区は、古くから国際交流の要衝として栄えてきた港町です。古代より朝鮮半島や中国大陸と交易があり、文化と技術が集まる“玄関口”としての役割を担ってきました。鎌倉時代には宋との交易によって織物技術が伝来し、これが博多織の起源とされています。
そして、町人文化が花開いた江戸時代にその価値が高まりました。博多商人は独自の美意識を育み、武士階級の礼装ともなる帯に格式と粋を求め、織物技術は磨かれていきました。また、博多祇園山笠をはじめとする地域の祭礼では、法被の上に博多帯を締めた男衆の姿が今も見られるように、織物は地域文化と密接に結びついています。
博多織の歴史
800年にわたる交易と改良の系譜
博多織の歴史は、時代の変遷とともに技術と格式を高め続けてきた、まさに“織りの日本史”です。
- 1241年(鎌倉時代):博多商人・満田彌三右衛門が僧侶とともに南宋に渡航し、織物技術を習得。帰国後に博多でその技術を伝承。
- 1490年代(室町時代):満田家の子孫・彦三郎が明に渡り、さらに高度な織技術を研究。帰国後に厚地の浮き模様織物(のちの献上博多)を開発。
- 1600年代初頭(江戸初期):黒田長政が福岡藩の藩主に就任。博多織を江戸幕府への献上品と定め、「献上博多」として格式を得る。
- 1700年代(江戸中期):武士階級を中心に博多帯の人気が広まり、「締めて緩まぬ帯」として評判に。
- 1800年代前半(江戸後期):町人の間でも博多帯が日常的に用いられ、縞柄や文様のバリエーションが増加。
- 1870年代(明治初期):ジャカード機導入により、紋紙による図案織りが可能に。製品の意匠性が飛躍的に向上。
- 1930年代(昭和初期):手織機と力織機の併用が一般化。献上柄に加え、現代的デザインの帯も登場。
- 1976年(昭和51年):博多織が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:ネクタイやバッグなどの現代的製品が人気を集め、ライフスタイル商品としての展開が進む。
博多織の特徴
伝統と実用が織り重なる、五感に響く帯文化
博多織の魅力は、視覚だけでなく、音や手触りといった感覚でも味わえる点にあります。特に「絹鳴り」と呼ばれる独特の音は、締める瞬間に絹糸同士がこすれて生じる“キュッ”という音で、品質の高さと密度の証とされています。
献上柄に代表される文様には、独鈷(とっこ)や華皿(はなざら)など仏具を図案化したものが多く、かつての献上品としての格式と、商人たちの信仰心が織り込まれています。なかでも「親子縞」は、太縞と細縞が交互に並ぶことで家族の絆を象徴する意匠として愛されてきました。
また、「朝締めても夕方まで緩まない」という帯の特徴は、絹糸を強く打ち込んだ緯糸の構造に由来しており、実用性と耐久性を兼ね備えた織物として、武士たちからの信頼を得ました。

博多織の材料と道具
絹の艶と強さを最大限に引き出す、博多の織技術
博多織は、素材選びと糸作り、織機の調整に至るまで、すべてが精密な手仕事に支えられています。
博多織の主な材料類
- 生糸(絹糸):国内外の高品質な繭から採取。艶・強度・染色性に優れる。
- 染料:先染め用に厳選された化学・天然染料が用いられる。
- 緯糸束:複数本をより合わせて太い糸に仕立て、打ち込み用に使用。
博多織の主な道具類
- 筬(おさ):緯糸を打ち込む際に用いる櫛状の道具。博多織のコシを生む要。
- ジャカード機:紋紙により模様を自動制御する織機。意匠の幅を広げた革新技術。
- 力織機:現在の主流。手織よりも効率的に、厚みと密度を確保できる。
- 手織機(高機):伝統の手織りによる繊細な織り表現に使用される。
素材の品質と、職人の感覚が融合することで、見る者・締める者を魅了する織物が生み出されます。
博多織の製作工程
絹に命を織り込む、五感で挑む博多の仕事
博多織の製作は、一本一本の糸から始まり、すべての工程に職人の手と目が求められます。
- デザイン・設計
模様・配色・用途に応じて図案を設計。伝統柄から現代的デザインまで多様。 - 染色
生糸を丁寧に洗浄・精練し、先染めで鮮やかな色彩を施す。 - 整経・機掛け
経糸を設計通りに並べ、織機にセット。糸の張力や間隔が仕上がりを左右する。 - 緯糸の準備(横合わせ)
数本の細い緯糸をより合わせ、太い緯糸に仕立てる。 - 製織(織り上げ)
筬で強く打ち込むことで厚みと模様を形成。熟練の織師が微妙な力加減で織り進める。 - 仕上げ・検品
織り上がった布を整理・蒸し・検品し、帯や製品へ加工。
一反の帯に込められた時間と技術は、まさに絹の芸術とも言えるもの。博多織は、技と魂が宿る“締める文化”の粋を今に伝えています。
800年の時を超えて進化を続ける博多織は、ただの織物ではありません。格式と実用、粋と信仰が織り込まれた文化の結晶です。絹が奏でる音と光の美を五感で楽しめるこの織物は、現代の暮らしの中にも確かな存在感を放ち続けています。











