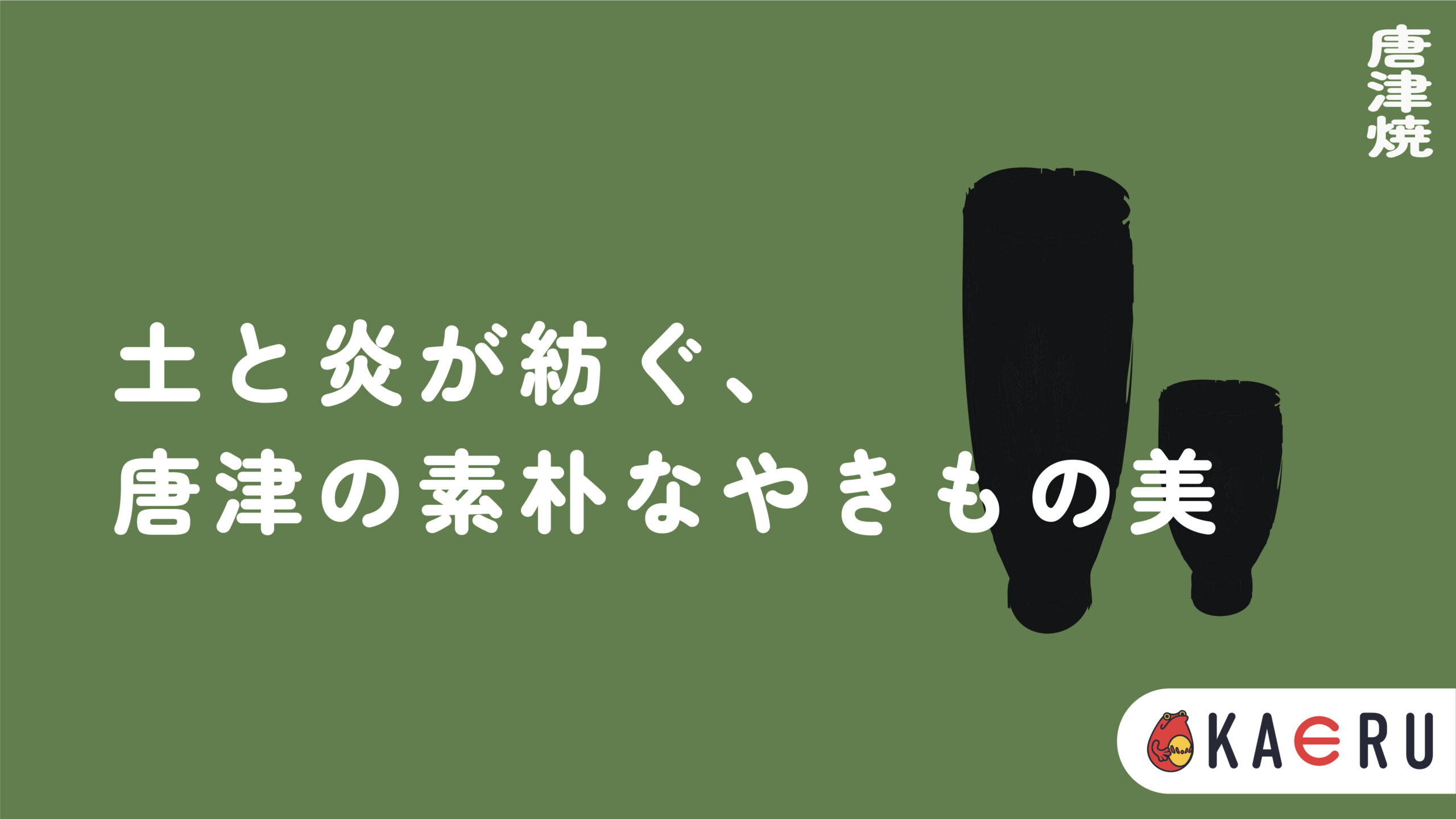唐津焼とは?

唐津焼(からつやき)は、佐賀県唐津市とその周辺で作られている日本を代表する陶器の一つです。安土桃山時代に始まり、400年以上の歴史を持つ唐津焼は、茶道具としてとりわけ高い評価を受け、「一楽二萩三唐津」と称されるほどに茶の湯の世界で重んじられてきました。
その魅力は、釉薬や焼成によって自然に生まれる表情と、土本来の温もりを活かした造形にあります。作為を控え、素材の素朴さや偶然の景色を尊ぶ唐津焼は、まさに「侘び寂び」の精神を体現するやきものと言えるでしょう。
| 品目名 | 唐津焼(からつやき) |
| 都道府県 | 佐賀県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1988(昭和63)年6月9日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |
| その他の佐賀県の伝統的工芸品 | 伊万里焼・有田焼(全2品目) |

唐津焼の産地
海風と土が織りなす、茶陶文化の源流

主要製造地域
唐津焼の主産地は、佐賀県唐津市を中心に伊万里市、武雄市、さらには長崎県松浦市など広域にわたります。玄界灘に面したこの地域は、海運の要衝として古くから交易が盛んで、16世紀末には朝鮮半島から多くの陶工が渡来し、本格的な登窯技術と施釉陶器の技法がもたらされました。これは「文禄・慶長の役」に伴う陶工招致の結果でもあり、唐津地域は日本陶芸史における一大変革地となりました。
また、茶の湯が戦国武将や豪商の間で広がる中、唐津焼はその素朴な風合いと自然な景色によって高く評価されました。唐津は長崎・博多といった交易港とも近く、朝鮮や中国の美意識とも接点が多く、独自の感性を育む下地がありました。加えて、江戸時代には藩主の庇護を受け、御用窯としての格式も確立されています。
気候的には、冬に冷え込み夏は多湿という九州北部特有の気候が陶土の性質と向き合う上で重要な要素でした。地元の陶土は鉄分を含み、水分をよく吸収するため、気温・湿度との調和が求められる素材であり、この土地ならではの技術適応が進化を促しました。また、登窯での焼成には松の薪が不可欠ですが、周囲の山地には薪材に適した赤松が豊富に存在しており、環境的にも恵まれた土地だったのです。
このように、唐津焼の産地は、歴史的背景、文化的土壌、自然環境の三位一体によって、400年を超える茶陶文化の中心地として発展を遂げてきたのです。
唐津焼の歴史
茶人に育まれた“侘びの陶”の系譜
唐津焼は、朝鮮陶工の技術移入を契機に発展し、茶道文化のなかで確固たる地位を築いたやきものです。
- 1580年代: 朝鮮陶工の渡来により、唐津周辺に初の登窯が築かれ、灰釉・鉄絵など多彩な技法が導入される。
- 1592年(文禄元年): 文禄の役での陶工招致により、肥前一帯で施釉陶器の生産が本格化。
- 1600年代初頭(慶長年間): 唐津藩の保護下で藩窯が整備され、主に茶碗・皿・壺などの生活陶器が量産される。
- 1620年代: 絵唐津・斑唐津・朝鮮唐津といった様式が確立され、茶人たちの間で重用され始める。
- 1650年代: 有田での磁器生産が隆盛し、唐津焼の輸出用途は減少するが、茶道具としての価値が定着。
- 1700年代中頃: 地元豪商や武家により注文生産が増え、個性的な造形が生まれる。
- 1880年代(明治20年代): 産業構造の変化で一部窯元が廃絶するも、民藝運動以前から再評価の兆しが見え始める。
- 1930年代(昭和初期): 柳宗悦・濱田庄司らの民藝運動により、唐津焼の素朴な魅力が再発見される。
- 1988年(昭和63年): 唐津焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代: 若手作家や新窯元の台頭により現代的な唐津焼が登場。国内外の茶人・美術愛好家から注目を集めている。
唐津焼の特徴
偶然に宿る景色を愛でる、土と火の芸術
唐津焼の最大の魅力は、作為を排した素朴な造形と、自然が生んだような表情にあります。釉薬の流れ、炎の加減、薪の灰がつくる窯変(ようへん)など、狙ってできない“景色”を愛でるのが唐津焼の醍醐味です。茶人に好まれた理由の一つに、「使うほどに味わいが深まる」ことが挙げられます。たとえば、粉引唐津の茶碗は使い込むほどに貫入(かんにゅう)と呼ばれる細かなヒビが入り、そこに茶が染み込むことで景色が変化します。これを「育てる器」と表現することもあります。
また、唐津焼は器の“裏”にも美が宿ります。高台の削り跡、指で釉薬を留めた「指跡」、釉薬が流れ止まった「溜まり」など、すべてが意図を超えた自然の演出となります。これは「侘び寂び」の精神に通じるものであり、完璧でないものに価値を見出す日本美の結晶ともいえるでしょう。

唐津焼の材料と道具
土の力を引き出す、火と技の融合
唐津焼では、地元の陶土を中心に、素朴な素材感と焼成の偶然性を生かす技法が用いられます。釉薬の流れや焦げなど、自然の表情を尊ぶ姿勢が道具選びにも反映されています。
唐津焼の主な材料類
- 唐津陶土:鉄分を含み、焼成で灰色〜赤褐色になる土。
- 釉薬各種:藁灰釉・木灰釉・鉄釉など、土と釉の相性を生かす自然釉。
- 藁や灰:釉薬の原料や焼成時の景色づくりに活用。
唐津焼の主な道具類
- ロクロ:手引きによる成形を行う。
- カンナ:高台整形や面取りなどに使用。
- 筆:絵唐津の絵付けに使用する鉄絵具用筆。
- 登窯:大量焼成かつ独特の景色を生む薪窯。
素朴な素材に手仕事と火が加わることで、唐津焼ならではの景色と温もりが生まれるのです。
唐津焼の製作工程
土に命を吹き込む、窯と対話する仕事
唐津焼は、土の選別から焼成まで、多くの工程を経て完成します。とりわけ焼成は、登窯の炎との対話であり、偶然性も作品の一部とする寛容な美意識が息づいています。
- 土づくり
陶土を砕き、水簸して不純物を除く。熟成後、成形用に調整。 - 成形
手ロクロで一つひとつ形を作る。用途により板作りや型押しも。 - 乾燥・削り
高台や表面の調整を行い、乾燥させる。 - 施釉・絵付け
技法に応じて釉薬をかける。鉄絵具での絵付けも。 - 焼成
登窯や穴窯などで長時間焼成。薪の火力や灰が自然の景色を生む。 - 仕上げ・検品
焼き上がりを見て、ひとつひとつ丁寧に仕上げる。
唐津焼は、器そのものに景色を宿す「用の美」の極致。土と火、偶然と必然が融合した、現代に息づく茶陶の名品です。
唐津焼は、自然と職人の感性が織りなす、日本が誇る茶陶の名品です。素朴で力強く、偶然に生まれる景色を美とするその姿勢は、現代の暮らしにも静かに寄り添います。日々使う中で深まる味わいと共に、唐津焼は今もなお生き続けています。