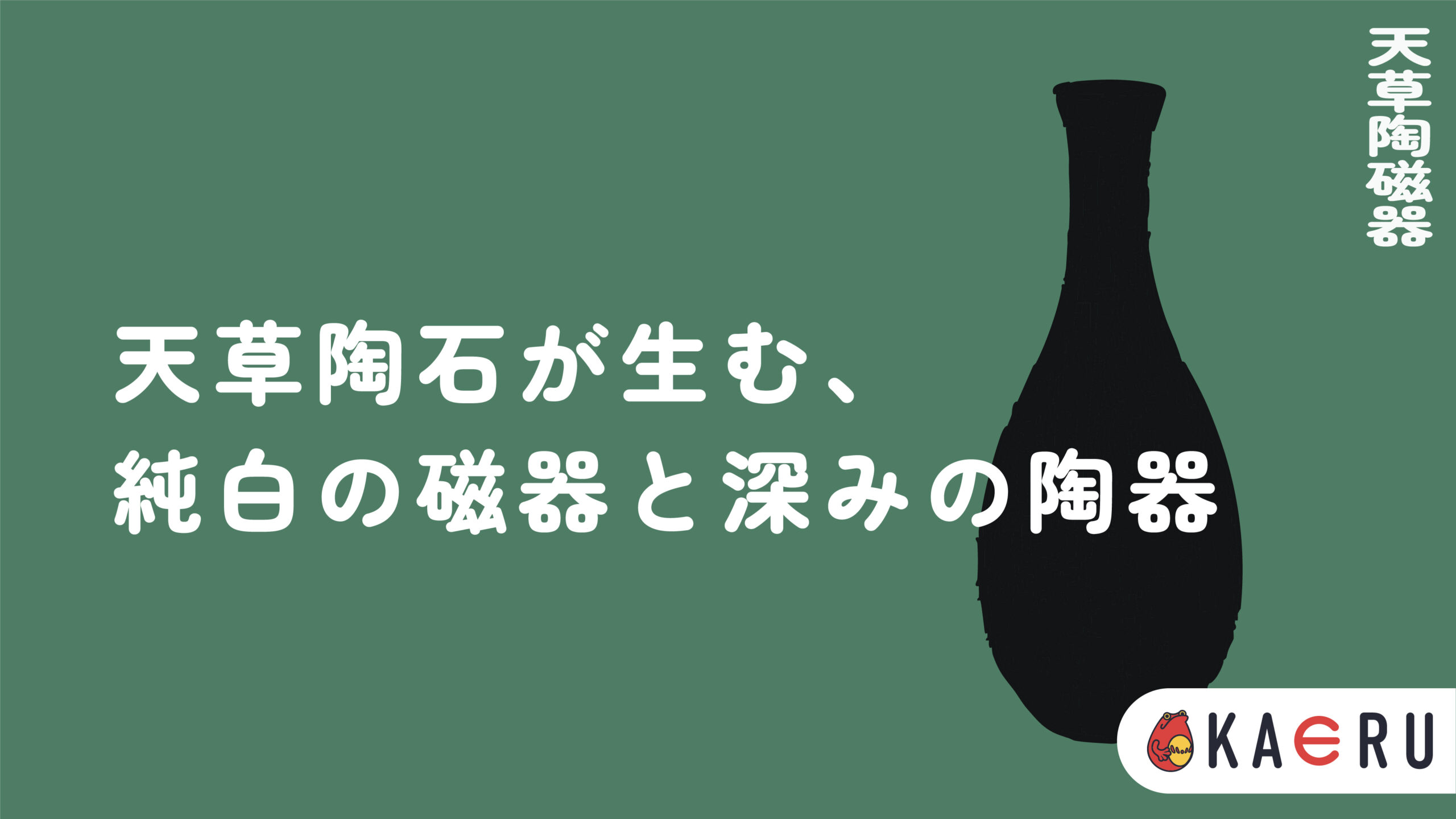天草陶磁器とは?

天草陶磁器(あまくさとうじき)は、熊本県天草市周辺で作られている伝統的な陶磁器です。主に二つの系統があり、ひとつは日本一と評される純度の高い「天草陶石」を原料とした白磁、もうひとつは地元の陶土を使った温もりある陶器です。磁器は、にごりのない透明感と滑らかな肌合いを持ち、器としての機能美と清廉な佇まいが魅力。陶器は、海鼠釉(なまこゆう)や黒釉(こくゆう)といった釉薬を重ね掛けすることで、奥行きある色調や趣を醸し出します。
素材の良さを最大限に生かしながら、多彩な表情を持つ器を生み出すのが天草陶磁器の大きな特徴です。
| 品目名 | 天草陶磁器(あまくさとうじき) |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 2003(平成15)年3月17日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(2)名 |
| その他の熊本県の伝統的工芸品 | 小代焼、肥後象がん、山鹿灯籠(全4品目) |

天草陶磁器の産地
陶石と陶土の恵みが育んだ、海のやきもの文化

主要製造地域
天草陶磁器の産地である熊本県天草市は、大小120以上の島々からなる天草諸島を中心とする地域です。この地は、地質学的に非常に特異な地形を持ち、白く輝く高純度の陶石(天草陶石)を豊富に産出することで知られています。この陶石は国内磁器原料の約8割を供給するとも言われ、有田焼・波佐見焼・美濃焼など日本有数の磁器産地にとっても重要な供給源となっています。
文化的にも、天草は長崎との結びつきが強く、江戸期には南蛮文化やキリシタン文化の影響が及ぶなど、外来の技術や感性を受け入れる風土がありました。陶芸技術の導入や釉薬表現の多様性など、外部との文化交流の影響が焼き物にも色濃く表れています。また、海路を通じて有田や唐津、薩摩など周辺の産地とも技術的な往来があり、磁器と陶器の両系統を併せ持つ特性もこうした背景から生まれたと考えられています。
また、温暖な海洋性気候に恵まれ、湿度や温度の変化が比較的穏やかであることから、土づくりや乾燥工程にも適した土地柄です。また、薪に適した雑木林も豊富で、登り窯の燃料供給にも恵まれていました。
こうした自然資源、文化交流、気候条件が三位一体となって、天草独自の陶磁文化を形成してきたのです。
天草陶磁器の歴史
磁器と陶器、二つの系譜が紡ぐやきもの史
天草陶磁器は、磁器と陶器という性質の異なる二系統を併せ持つ焼き物です。
- 1670年代(寛文年間): 有田焼の陶工が天草へ移住し、磁器生産を開始。良質な陶石が高く評価される。
- 1690年代(元禄期): 天草陶石の採掘が本格化。有田焼の原料供給地として地位を確立。
- 1770年代(安永年間): 地元の粘土を使った陶器製造が始まる。日用品や茶器が中心。
- 1820年代(文政年間): 海鼠釉・黒釉の試作が行われ、装飾陶器としての表現が拡大。
- 1889年(明治22年): 天草に登り窯が導入され、量産体制が整う。
- 1925年(大正14年): 九州陶磁器展にて天草陶磁器が初入賞。作家的制作が注目されはじめる。
- 1955年(昭和30年): 経済復興とともに食器類の生産が拡大。地元市場と観光需要に応える。
- 2003年(平成15年): 天草陶磁器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代: 海外評価の高まりとともに、現代的な器やアートピースの製作も進む。
天草陶磁器の特徴
磁器の白、陶器の深、二つの表情が共存する、天草ならではの焼き物
天草陶磁器の魅力は、その「二面性」にあります。ひとつは、天草陶石から生まれる磁器。もうひとつは、地元陶土を使った陶器。このふたつが、ひとつの産地で共存している点は、日本の伝統工芸においても珍しいケースです。
磁器では、まるで雪のように澄んだ白さと、すべすべとした光沢が特筆されます。特に薄手に仕上げられた器は、持ったときの軽さに驚かされると同時に、その見た目からは想像できないほどの強度を備えています。まさに「美しさと実用の両立」がなされた器なのです。
一方の陶器は、焼成の工程で流れるように動く釉薬によって独特の風合いを生み出します。海鼠釉は、焼成中に流れ落ちることで、波のような模様を器の表面に描き、まさに「海を見た陶器」と言える趣があります。また、黒釉を重ねることで、墨のような奥行きある色合いを出すことも可能です。
天草陶磁器には「二重掛け」と呼ばれる釉薬の重ね技法があります。異なる性質の釉薬を順に掛けることで、焼成時に化学反応が起こり、偶然性のある美しい文様が現れます。同じ釉薬でも二つとして同じ表情にはならない、そんな“焼き物の一期一会”を楽しめるのも天草陶磁器ならではの魅力です。

天草陶磁器の材料と道具
白と深色を引き出す、天草ならではの素材力と技の冴え
天草陶磁器は、陶石と陶土という異なる素材を使い分け、それぞれに適した道具と工程で仕上げられます。
天草陶磁器の主な材料類
- 天草陶石:全国でも評価の高い高純度の白色陶石。磁器用。
- 地元の陶土:やや粗めで鉄分を含み、温かみのある色合いに仕上がる陶器用土。
- 海鼠釉:青黒く光沢のある釉薬。高温焼成で流れ模様を描く。
- 黒釉:深みある黒色を出す釉薬。重厚な印象を与える。
天草陶磁器の主な道具類
- 轆轤(ろくろ):成形用。手回しや電動が使われる。
- ヘラ・コテ:成形や削りに使う各種道具。
- 筆・スポイト:釉薬の施釉や文様描きに使用。
- 焼成用窯:ガス窯や電気窯のほか、登り窯を用いる窯元も。
素材の選定から釉薬の掛け方まで、細やかな調整と経験がものをいう世界です。
天草陶磁器の製作工程
素材の個性を焼き上げる、磁器と陶器それぞれの道
天草陶磁器の製作工程は、素材の種類によって異なりますが、代表的な流れは以下のとおりです。
- 原料選別・精製
陶石は粉砕・沈殿・脱水処理で純度を高め、陶土は篩(ふるい)と水簸で成形に適した状態に整える。 - 成形
主に轆轤を用いて器を形づくる。磁器は薄く、陶器はやや厚みのある造形が多い。 - 乾燥・素焼き
完全に乾燥させたのち、800度前後で素焼きする。これにより強度が増し、施釉しやすくなる。 - 施釉(せゆう)
海鼠釉や黒釉などを単掛けまたは二重掛けで施す。筆やスポイトなどで意匠を加えることもある。 - 本焼き
約1,250度の高温で焼成。釉薬が溶けて器肌と一体化し、色味や質感が決まる。 - 仕上げ
高台の削りやバリ取りなどを行い、器としての安全性と美しさを整える。
こうした緻密な工程を経て、天草陶磁器はその完成度の高い姿を現します。
天草陶磁器は、磁器と陶器の魅力を一つの産地で楽しめる稀有な存在です。素材の純度を生かした白磁と、釉薬が織りなす陶器の景色。その両極が共存することで、多彩で個性的な器たちが生まれています。自然と人の技が調和した、暮らしに寄り添う焼き物文化です。