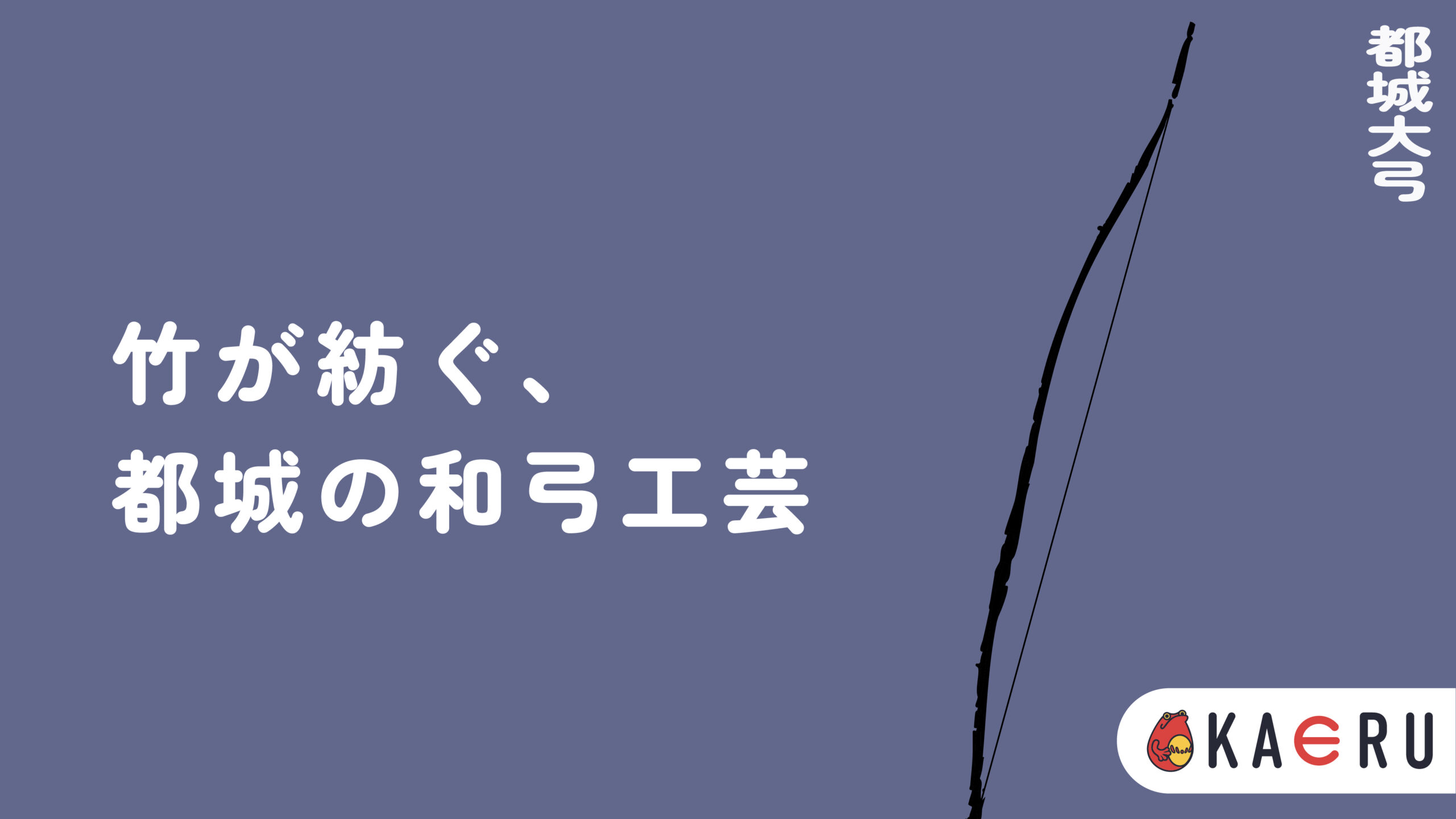都城大弓とは?
都城大弓(みやこのじょうおおゆみ)は、宮崎県都城市と三股町を中心に製作される、日本古来の長弓(和弓)です。国内流通する竹弓の9割を占める一大産地であり、その製作技術は江戸時代初期から続くとされ、今日も200以上の工程を弓師が一貫して手仕事で行っています。
最大の特長は、良質なマダケとハゼノキを使い、弾力性と耐久性、そして美しさを兼ね備えた弓に仕上がる点にあります。都城大弓は、単なる武具や競技道具にとどまらず、日本の自然と職人の精神が融合した伝統工芸品として、高い評価を受けています。
| 品目名 | 都城大弓(みやこのじょうだいきゅう) |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 1994(平成6)年4月4日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 4(10)名 |
| その他の宮崎県の伝統的工芸品 | 本場大島紬(全2品目) |

都城大弓の産地
薩摩の武士文化と豊かな自然が育んだ、和弓の聖地

主要製造地域
都城大弓の産地である宮崎県都城市・三股町は、九州山地と霧島連山に囲まれた内陸の盆地地帯に位置し、古くから農林業が盛んな地域として発展してきました。とりわけマダケの生育に適した火山灰土壌や豊かな雨量、昼夜の寒暖差など、竹の品質に大きく影響を与える自然条件が揃っており、「弓竹の名産地」として全国に知られるようになりました。
都城は薩摩藩の飛び地領であり、藩主・島津家の発祥の地でもあります。武家文化が色濃く残り、武具の製作や弓術の修練が盛んだった背景が、弓づくりの文化を地域に根付かせる土壌となりました。江戸時代には武士階級のみならず、庶民の間にも弓術が広まり、それに伴い高品質な弓への需要が増加。この地では「弓は都城」と呼ばれるほどに高い評価を得るようになりました。
文化的には、弓道という日本古来の礼法を重んじる武道が根づいていることから、都城市内では現在も小中学校で弓道教育が行われており、全国大会の開催地としても名を馳せています。地域の子どもたちに向けた出前授業や工房見学なども活発に行われ、弓の文化が世代を超えて引き継がれています。
都城大弓の歴史
薩摩武士の技と誇りを受け継ぐ、弓工芸の系譜
都城大弓は、武士の武具としての役割から始まり、長い時代を経て日本の工芸文化のひとつとして昇華されてきました。その歴史は400年以上におよび、地域の気風とともに深く根づいています。
- 1600年代初頭(江戸初期):薩摩藩の支藩としての都城で、武士の武具として弓の製作が始まる。島津家の武芸奨励により、弓術とともに技術が広まる。
- 1700年代中頃:マダケの選定法やハゼノキとの貼り合わせ技術が確立され、現在に通じる製法の基礎が築かれる。弓師という専門職が成立。
- 1800年代初頭(江戸後期):都城での弓製作が本格化し、薩摩藩内外への出荷が始まる。「薩摩弓」としての名声が高まり、都城の弓が地域ブランドとして認知される。
- 1870年代後半(明治10年代):廃藩置県後も武道としての弓術が続き、地元職人により民間製造が継承される。警察や学校での武道採用により需要が持続。
- 1890年代(明治30年代):職人の養成が進み、都城一帯に複数の弓工房が誕生。教育機関や民間道場向けに製品が広がる。
- 1930年代(昭和初期):品質の高さが評価され、台湾・朝鮮半島など東アジア諸国への輸出が行われる。全国的な知名度がさらに上昇。
- 1950年代(戦後復興期):学校教育における弓道の普及に伴い、全国から注文が殺到。都城が竹弓製作の一大供給地となる。
- 1994年(平成6年):都城大弓が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:出前授業や工房見学を通じた教育活動、新素材との融合による試作・研究も進行中。伝統を守りながら未来へ向けた進化が続いている。
都城大弓の特徴
一本の弓に宿る、自然の力と人の技の結晶
都城大弓の魅力は、何よりもその機能美と造形美が高次元で融合している点にあります。使用されるマダケは、寒さの厳しい季節に伐採され、油抜きや自然乾燥を経てしなやかで張りのある素材へと生まれ変わります。さらに、芯材に使われるハゼノキが加わることで、強度と弾力性のバランスが整い、長期間使っても型崩れしない弓が生まれます。
製作はすべて一人の弓師が行い、200以上にも及ぶ工程が分業ではなく一貫して手作業で施されるという点も特筆すべきです。これは弓一本ごとに材のクセや張り具合を見極め、最適な設計を行うためであり、まさに職人の目と手が頼りの精密な工程です。
完成した弓を引いたときに響く「ピン」と澄んだ音は、都城大弓ならではの特徴です。この音の余韻は弓道家の間で「心を整える音」とも言われており、集中力を高める助けにもなっています。
このように、都城大弓は、素材・技術・精神性すべてが揃ってこそ成り立つ、和弓文化の最高峰なのです。

都城大弓の材料と道具
自然とともに生きる、弓づくりの美学
都城大弓の製作には、自然素材と精緻な道具が不可欠です。地元の環境が生んだ素材と、熟練の手業によって、一本の弓が生まれます。
都城大弓の主な材料類
- マダケ(3~4年物):弓竹・芯竹として使用され、弾力と軽さに優れる。
- ハゼノキ:弓芯材として使われ、強度としなやかさを補完。
- 木炭:油抜き工程で使用。炭火で竹をあぶるための燃料。
- トウ(藤):握束部分に巻く紐として用いられる。
都城大弓の主な道具類
- 鉈(なた):竹の切り出しや割り作業に用いる。
- 小刀・削り鉋:竹やハゼ材を丁寧に削る道具。
- くさび:弓の形を定めるために80〜100本使用される木製の締具。
- はり台:弓の湾曲を形作る台座。
こうした素材と道具を用い、一本の弓が自然と職人の感性によって誕生するのです。
都城大弓の製作工程
200を超える細密な工程が紡ぐ、和弓の完成形
都城大弓は、弓師と呼ばれる職人が、自然の素材と対話しながら、200以上の工程を経て完成に至ります。
- 竹の切り出し
寒い時期に3〜4年育ったマダケを選び、伐採。用途に応じて弓竹・芯竹に割り分ける。 - 油抜き・自然乾燥
弓竹を炭火であぶり、浮いた油を丁寧に拭き取る作業を数回繰り返す。乾燥には数ヶ月を要する。 - 削り加工
竹をにぎり部分から両端にかけて薄く削り、しなりの曲線を整える。 - 打ち込み・張り合わせ
芯竹を弓竹ではさみ、額木・関板を取り付け、80〜100本の竹製くさびで圧締し湾曲をつける。 - はりこみ・弦張り
くさびを外して全体を整形し、弦を仮張りして反り具合や張力を最終調整する。 - 仕上げ・握束
表面を鉋で磨き、にぎり部分に天然藤を巻いて完成。
都城大弓は、素材・技術・感性のすべてが結晶した和弓の最高峰。現在でも全国の弓道家から絶大な信頼を集め、伝統と未来をつなぐ工芸として進化を続けています。
都城大弓は、自然素材の力を活かし、200以上の手仕事を経て一本ずつ仕上げられる、日本の伝統と職人技の結晶です。武具の歴史を起源に持ちつつも、美しさ・機能性・精神性のすべてを兼ね備えたこの弓は、現代の弓道家からも高く支持されています。都城の風土と文化が育んだ“究極の和弓”は、今も静かに、次の世代へと受け継がれているのです。