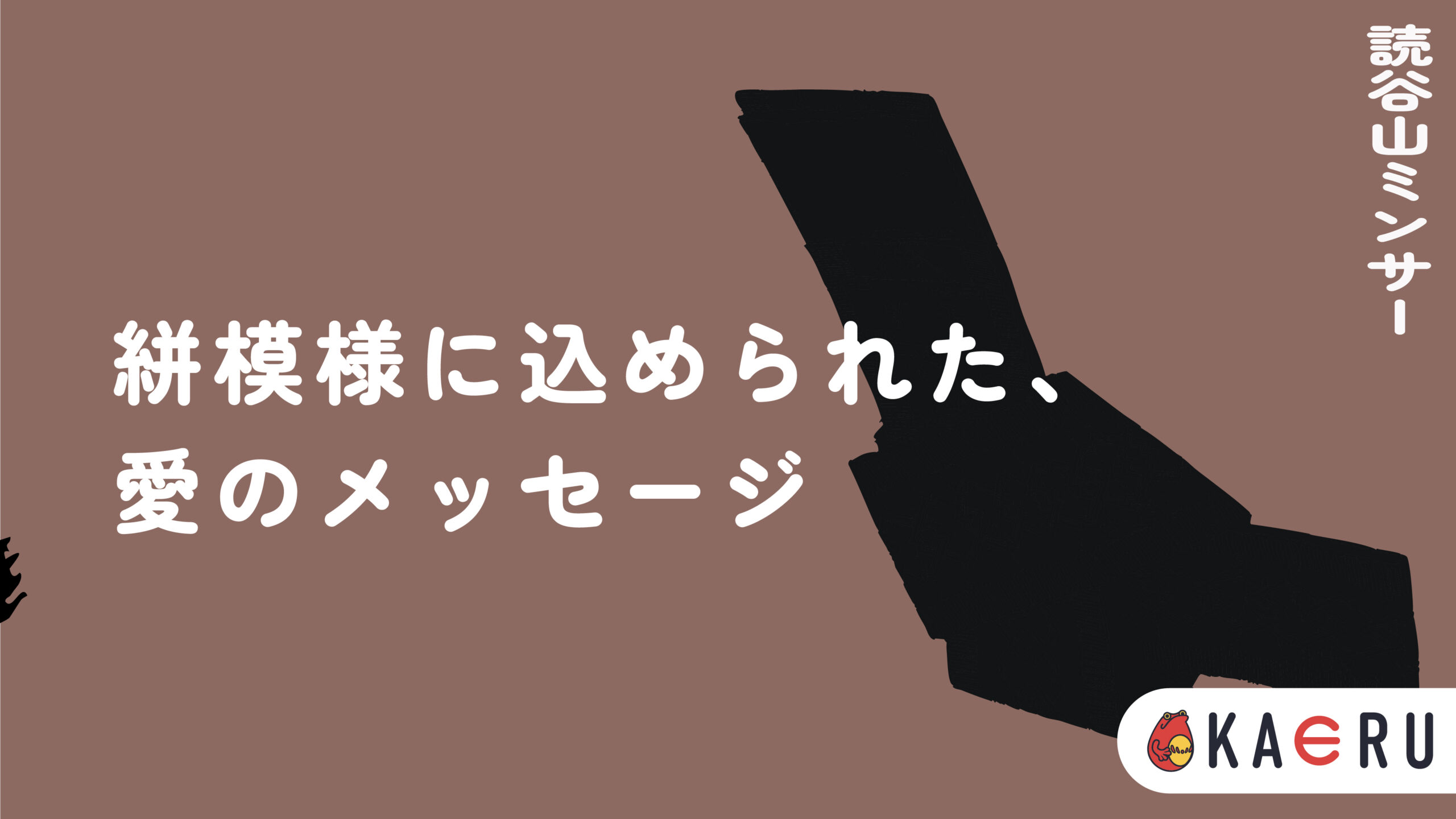読谷山ミンサーとは?
読谷山ミンサー(ゆんたんざみんさー)は、沖縄県読谷村で作られる綿織物で、主に細帯として用いられます。「ミンサー」は、木綿(ミン)と狭い帯(サー)を組み合わせた言葉が語源とされ、起源は17世紀頃にまでさかのぼると考えられています。
最大の特徴は、「五つと四つ」の絣(かすり)模様。「いつ(五つ)の世(四つ)までも末永く」という想いが込められた文様で、大切な人への贈り物として親しまれてきました。
一時は戦後の混乱で生産が完全に途絶えましたが、1970年代に読谷村の有志や研究者たちの協力によって復元活動が進められ、現在では沖縄を代表する伝統工芸品のひとつとして広く知られています。
| 品目名 | 読谷山ミンサー(ゆんたんざみんさー) |
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(1)名 |
| その他の沖縄県の伝統的工芸品 | 知花花織、久米島紬、宮古上布、読谷山花織、壺屋焼、琉球絣、琉球漆器、与那国織、八重山ミンサー、喜如嘉の芭蕉布、八重山上布、首里織、琉球びんがた、南風原花織、三線(全16品目) |

読谷山ミンサーの産地
海風とともに育まれた、読谷村の生活文化

主要製造地域
読谷山ミンサーの産地・読谷村は、沖縄本島中部の西海岸に位置し、古くから農業や工芸が盛んな地域として知られてきました。とくに女性たちの手仕事として受け継がれてきた織物文化は、村の暮らしと深く結びついています。
現在は、読谷山ミンサー会を中心とする工房や地元組合が、技術の保存と後継者育成に尽力しており、地元学校との連携や地域イベントなどを通じて、織物文化の価値を伝える活動が広がっています。
読谷山ミンサーの歴史
五四の文様に込められた、暮らしと祈りの記憶
読谷山ミンサーの歴史は古く、琉球王国時代から生活に根ざした織物として人々に親しまれてきました。その後、社会の変化とともに生産が一時途絶えましたが、1970年代に復興の機運が高まり、伝統が再び息を吹き返すこととなります。
- 18世紀:読谷地域で日常的な帯布としてミンサーが織られ始める。
- 明治〜昭和初期:木綿の需要減少や生活様式の変化により、ミンサーの生産が縮小。
- 戦後:戦禍と経済的混乱により、読谷山ミンサーの生産が完全に途絶。
- 1970年代:読谷村の有志と織物研究者の協力により、復元と継承活動が本格化。
- 1976年(昭和51年):読谷山ミンサーが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
読谷山ミンサーの特徴
五四の模様に込めた、愛と祈りの意匠
読谷山ミンサーのもっとも印象的な特徴は、「五つと四つ」の絣文様です。この文様は、沖縄において古くから「いつの世までも末永く」といった願いを象徴する模様として親しまれており、特に贈答用の帯などで重用されてきました。
使用される糸は主に木綿で、丈夫さと柔らかさを兼ね備えています。織りはすべて手織りで行われ、絣模様を均等に出すためには高い精度と経験が必要とされます。また、藍や草木染めの美しい色合いも魅力のひとつで、近年ではインテリア小物やファッション雑貨としても注目を集めています。

読谷山ミンサーの材料と道具
沖縄の自然とともに織り上げる、素材と技法
読谷山ミンサーには、沖縄の風土に根ざした素材と、手仕事ならではの道具が活用されています。
読谷山ミンサーの主な材料類
- 木綿糸:経糸・緯糸の両方に使われる基本素材。
- 藍染・草木染め:自然素材から抽出した染料で、深みのある色合いを生む。
- 化学染料:色の再現性と耐久性を高めるため併用される。
読谷山ミンサーの主な道具類
- 手機(てばた):絣模様の位置を調整しながら織るための織機。
- 絣括り道具:糸に模様を付けるための防染用具。
- 管巻き機:緯糸を巻き取るための補助具。
- 杼(ひ):緯糸を経糸の間に通す道具。
これらの素材と道具は、職人によって丁寧に管理・使用され、伝統的なミンサーの美しさと実用性を両立させています。
読谷山ミンサーの製作工程
暮らしの中に息づく、手織りの技
読谷山ミンサーの製作は、模様の設計から糸の準備、そして織りの工程まで、すべて手仕事で進められます。一つひとつの作業には、地域に伝わる知恵と職人の感性が息づいています。
- 図案の作成
五四模様や縞模様の構成を設計。 - 糸染め
藍や草木などを使い、絣部分や全体の色を染める。 - 整経・絣括り
絣模様が現れるよう、経糸を括って染め分ける。 - 製織
設計図に沿って、経糸と緯糸を手機で織り進める。 - 仕上げ
織り上がった布を整え、検反や仕立てを行う。
こうして完成した読谷山ミンサーは、素朴ながらも力強く、使い手の暮らしにそっと寄り添う存在として親しまれ続けています。