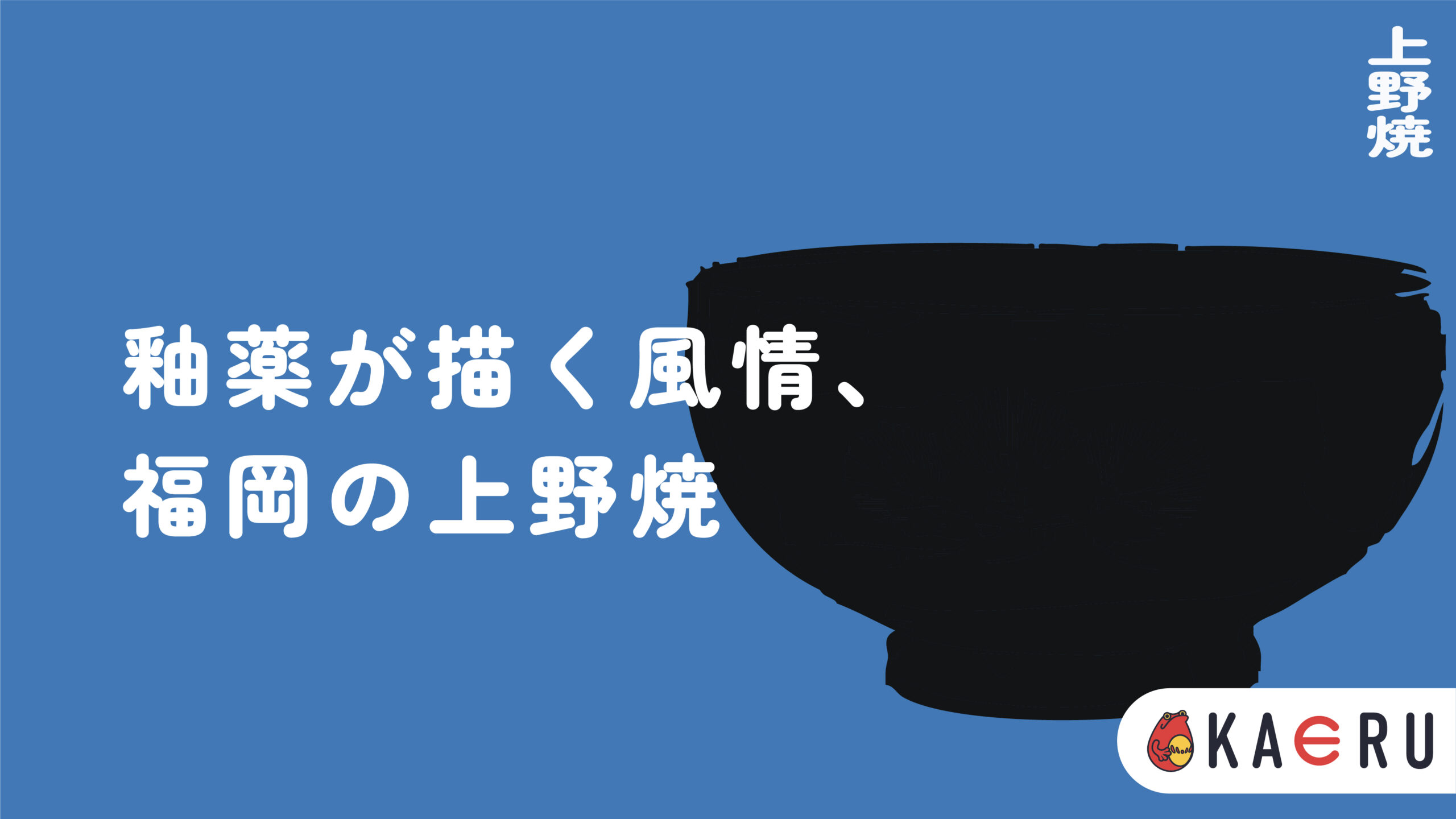上野焼とは?

上野焼(あがのやき)は、福岡県福智町にて生産される伝統的な陶器で、17世紀初頭より400年以上にわたる歴史を持ちます。茶人に愛された「遠州七窯」の一つとしても知られ、細川家・小笠原家などの藩主の御用窯として発展しました。
最大の特徴は、手に取ったときの心地よさを追求した「薄づくり」。さらに「緑青流し(ろくしょうながし)」をはじめとする釉薬の多彩な表情が、器ひとつひとつに個性と奥行きを与えています。侘び寂びの精神と繊細な技巧が融合した、まさに茶陶の美を体現する焼き物です。
| 品目名 | 上野焼(あがのやき) |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1983(昭和58)年4月27日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(14)名 |
| その他の福岡県の伝統的工芸品 | 久留米絣、小石原焼、博多織、八女福島仏壇、博多人形、八女提灯(全7品目) |
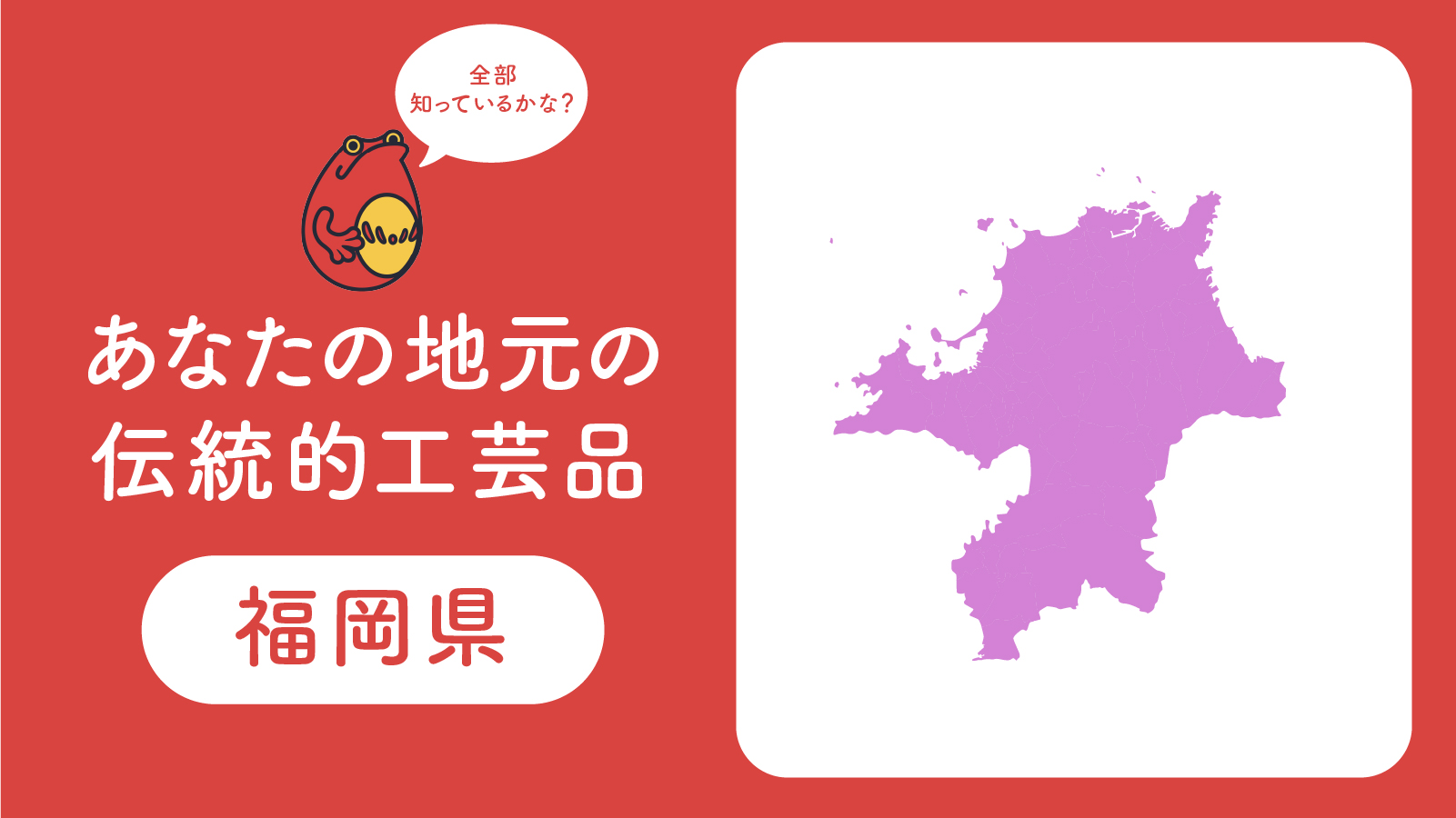
上野焼の産地
茶の湯文化と自然に恵まれた、焼き物の里・福智町

主要製造地域
上野焼の主産地である福岡県福智町は、福智山の麓に広がる自然豊かな地域です。当地は古くから良質な陶土層が広がり、清らかな水と松の薪が豊富に得られることから、焼き物づくりに理想的な地理的条件を備えていました。
江戸初期の1602年、豊前小倉藩主・細川忠興がこの地に李朝陶工・尊楷(そんかい)を招いて開窯したことが始まりとされています。 この開窯は、単なる技術導入ではなく、茶人でもあった忠興が理想の茶陶を追求する中で生まれた文化政策の一環でした。以降、藩の御用窯として保護を受け、上野焼は武家文化や茶の湯文化の中核を担う存在へと成長していきます。
また、小堀遠州によって「遠州七窯」のひとつに選ばれるなど、上野焼は侘び寂びの精神を体現する茶陶として全国の茶人に高く評価されてきました。 江戸期を通じてその美意識は一貫しており、明治以降もその気品を守りながら、現代の作家たちによって新たな表現が加えられています。
上野焼の歴史
茶人たちの審美眼に応えた、用の美の系譜
上野焼は、17世紀初頭から続く国焼(くにやき)の名窯として、武家文化・茶道文化と深く結びつきながら発展してきました。
- 1602年:豊前小倉藩主・細川忠興が、朝鮮からの陶工・尊楷を上野に招き、窯を開く。茶陶を主目的とした御用窯としての出発。
- 1615年:大坂の陣ののち、細川家が熊本へ転封。上野焼は新たな藩主・小笠原家のもとで存続し、御用窯として重用される。
- 1620年代〜1650年代:釉薬の技術が進化。藁灰釉や鉄釉などが用いられ、独自の釉調が確立。
- 1680年代:小堀遠州により「遠州七窯」のひとつに選定される。茶人の間で知名度と格式が高まる。
- 1700年代〜1800年代初頭:江戸期を通じて藩の庇護のもと技術と意匠が洗練される。茶人好みの薄づくりが定着。
- 明治維新以降:藩の保護を失い一時衰退。民間の陶工による自立経営が始まる。
- 1930年代(昭和初期):地元有志により伝統の再評価が進み、再興の機運が高まる。
- 1983年(昭和58年):上野焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:伝統技法に加え、現代的意匠の作品も登場。個展や海外展示など表現の幅が拡大。
上野焼の特徴
軽やかで気品ある「薄づくり」と、唯一無二の釉薬表現
上野焼の最も際立った特徴は、「薄づくり」にあります。見た目には繊細で儚く、それでいて手に持つとしっかりとした質感と安定感を感じさせる。その絶妙なバランスが、手仕事の温もりと用の美を見事に融合させています。
この薄さを可能にするのは、長い時間をかけて精製された陶土。水に晒し、布に包み、数ヶ月間寝かせるという手間を惜しまない土づくりによって、轆轤で精緻に挽いても割れにくく、釉薬との相性にも優れた粘土が生まれます。
釉薬表現もまた、上野焼の奥深さを物語ります。「緑青流し」と呼ばれる銅を使った青緑色の流れ模様は、窯の内部で空気と反応し、複雑な色の変化を生み出します。焼成時の酸素量や温度、窯内の位置によっても表情が変わるため、ひとつとして同じものはなく、器それぞれがまるで自然の景色のような個性を持っています。

上野焼の材料と道具
命を吹き込むのは、土と釉の絶妙なバランス
上野焼の製作は、陶土と釉薬の緻密な管理から始まります。特に「薄づくり」を実現するためには、素材の純度と粘性が極めて重要とされます。
上野焼の主な材料類
- 上野の陶土:地元産の粘土。不純物を徹底的に除去し、水に晒して寝かせる工程を経て使用。
- 釉薬各種:初期は藁灰・ススキ灰による自然釉が主流。現在は銅釉・鉄釉なども活用。
- 燃料(松):炎の質を左右する大切な要素。登り窯や穴窯の焼成に使われる。
上野焼の主な道具類
- 轆轤(ろくろ):薄づくりの器形を生み出す基本道具。
- カンナ・削りべら:成形後の細部調整に用いる。
- 釉掛け用道具:流しかけや浸し掛けなど、多彩な釉掛け技法に対応。
- 窯道具(棚板・支柱):焼成中の変形や釉薬垂れを防ぐための補助具。
こうした素材と道具の緻密な調和が、繊細な器の完成度を高めています。
上野焼の製作工程
ひとつひとつに個性を宿す、茶陶の創作プロセス
上野焼の製作工程は、素材の選別から焼成に至るまで、一貫して手仕事と自然の対話によって成り立っています。
- 土づくり
陶土を採取後、水晒しと灰汁抜き、不純物の除去を行い、布に包んで水分を抜き、さらに数ヶ月寝かせる。 - 成形
轆轤で薄く引きながら器形をつくる。薄くても強度を保つ技術が必要。 - 乾燥・素焼き
湿度調整しながらゆっくり乾かし、800℃前後で素焼きする。 - 釉掛け
緑青流しなど、流しかけ・浸し掛け・重ね掛けなどの技法で釉薬を施す。 - 本焼き
1250℃前後の高温で焼成。登り窯や電気窯が使われ、窯変を期待した配置も工夫される。 - 仕上げ・検品
焼き上がりを一点ずつ確認し、底面研磨や歪み調整を行い完成とする。
この一連の工程の中で、自然素材の個性と炎の偶然性が融合し、唯一無二の器が生まれます。上野焼は、職人の手と自然の対話が紡ぐ、侘びと雅の焼き物文化なのです。
上野焼は、400年の伝統に培われた茶陶の美意識と、土と炎が生む偶然の妙が融合した焼き物です。手に馴染む薄づくりと釉薬の繊細な表情が、現代の暮らしにも調和し、唯一無二の存在感を放ちます。