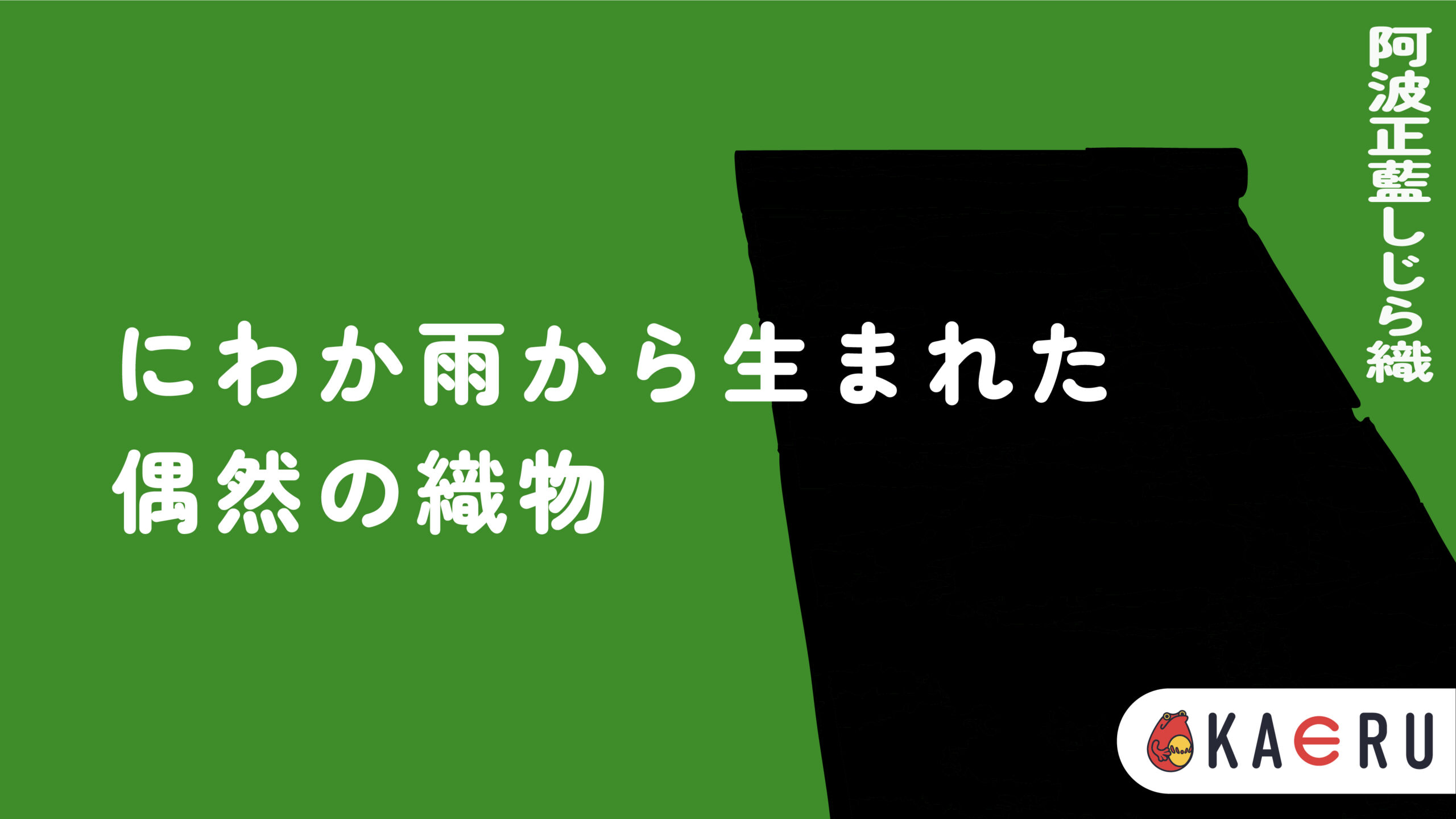阿波正藍しじら織とは?
阿波正藍しじら織(あわしょうあいしじらおり)は、徳島県で作られる藍染の綿織物です。江戸期に織られていた「たたえ織」を原型に、明治初期に偶然の雨と陽光から生まれた「しぼ(凹凸模様)」を活かした織物として発展しました。
最大の特徴は、徳島県産の藍から作られる天然染料「すくも」で丁寧に染め上げられる深い藍色と、肌に張りつかず軽やかな着心地を生む「しぼ」の風合いにあります。現在では夏の着物や浴衣だけでなく、ストールやバッグなど多彩な製品に展開され、現代のライフスタイルに寄り添う伝統工芸品として親しまれています。
| 品目名 | 阿波正藍しじら織(あわしょうあいしじらおり) |
| 都道府県 | 徳島県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1978(昭和53)年7月22日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(13)名 |
| その他の徳島県の伝統的工芸品 | 大谷焼、阿波和紙(全3品目) |

阿波正藍しじら織の産地
藍と暮らしが根づく、徳島の風土が織物を育む

主要製造地域
阿波正藍しじら織の主産地は、徳島県徳島市とその周辺地域です。ここは古くから「阿波藍」の一大生産地として知られ、江戸時代には全国有数の藍の集散地でもありました。吉野川の清流と豊かな地下水に恵まれ、染料づくりや水洗いに最適な環境が整っていたことが、藍染め文化の発展を支えました。
阿波藍を通じて染織や商業が発展し、庶民の衣生活を支える地場産業として綿織物も広まりました。特に19世紀後半以降は、藍染の浴衣や着物が日常着として定着し、染めと織りの分業制による生産体制が地域に根づいていきました。
また、徳島は温暖で湿潤な気候をもち、夏は高温多湿となるため、通気性があり、汗ばむ季節でも肌に張りつかないしじら織の着物はまさに気候風土に適した衣料品でした。日差しの強い風土も、染めた糸や布の天日干しに向いており、「しぼ」が生まれる乾燥工程に欠かせない条件となっています。
こうした自然・文化・産業が三位一体となって、阿波正藍しじら織という土地に根ざした織物文化が築かれてきたのです。
阿波正藍しじら織の歴史
にわか雨から生まれた偶然が、伝統になるまで
阿波正藍しじら織の歩みは、ひとつの「偶然」をきっかけに始まり、やがて地域の代表的な織物文化へと昇華していきました。
- 1700年代(江戸中期):徳島藩の奨励により、藍栽培が拡大。「阿波藍」と呼ばれる藍の葉が全国に流通。
- 1866年(慶応2年):徳島市安宅村の女性・海部ハナが、雨に濡れた綿織物を干した際、自然に生じた凹凸(しぼ)に着目。これがしじら織の原点とされる。
- 1870年代(明治初期):海部ハナが、糸の張力差や湯通しによって「しぼ」を意図的に生み出す製法を確立。従来の「たたえ織」が進化し、阿波しじら織が誕生。
- 1918年頃(大正7年頃):軽く涼しい着心地が評判を呼び、夏用着物・浴衣として全国的に需要が拡大。徳島県内で年間生産反数150万反、織元数200軒以上と最盛期を迎える
- 1978年(昭和53年):阿波正藍しじら織が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:浴衣や着物に加えて、シャツやストールなど現代の衣料・雑貨製品へと応用が広がり、藍染の魅力が再注目されている。
阿波正藍しじら織の特徴
藍としぼが織りなす、風の通う肌ざわり
阿波正藍しじら織の魅力は、視覚と触覚の両面にあります。まず一つ目は、深みと透明感を併せ持つ「阿波藍」の青。徳島の土壌と発酵技術から生まれる天然染料「すくも」で糸を染め上げることで、合成染料にはない奥行きのある藍色が生まれます。
そしてもう一つは、「しぼ」と呼ばれる表面の波状の凹凸。この独特の風合いは、糸の収縮率の違いや後工程での湯通しによって自然に生まれるもので、肌に張り付きにくく、汗をかいても涼やかな着心地を保ちます。
かつては浴衣や夏着物が中心でしたが、現在はシャツやネクタイ、ストールなどの現代的な製品へも応用され、その「揺らぎの美」と軽やかさは、多くの人を魅了し続けています。

阿波正藍しじら織の材料と道具
藍と綿、道具と手技が織りなす職人の感性
阿波正藍しじら織の製作には、徳島の自然から得られる染料と、織物の伝統を支える繊細な道具類が欠かせません。
阿波正藍しじら織の主な材料類
- 綿糸:通気性に優れ、染料をよく吸う。天然繊維ならではの柔らかさが特徴。
- すくも:阿波藍の葉を発酵・熟成させた天然染料。徳島独自の藍の原料。
阿波正藍しじら織の主な道具類
- 大谷焼の藍甕(かめ):染液の発酵に使う陶器の容器。藍の花を育てる場。
- 綛(かせ)あげ器:原糸を糸束にするための装置。
- 織機(おりき):経糸と緯糸を組み合わせて布を織る。手織りと機械式がある。
- 染色道具一式:竹製の棒、藍液撹拌棒、脱水器など。
阿波正藍しじら織の工程では、すべての道具と素材が、藍の色としぼの風合いを最大限に引き出すために用いられています。
阿波正藍しじら織の製作工程
藍と風を織り込む、四季を映す布づくり
阿波正藍しじら織の製作工程は、大きく4段階に分けられ、いずれも繊細な感覚と手仕事を要します。
- 綛あげ(かせあげ)
原糸を一本一本巻き取り、「綛(かせ)」と呼ばれる糸束に整えます。これは染めの均一性と作業性を高める準備工程です。 - 染色(そめ)
綛を藍甕に浸けて染色します。空気に触れて酸化することで、淡い青から徐々に深い藍色へ変化していきます。染め・水洗い・天日干しを複数回繰り返すことで、色の層に深みが生まれます。 - 製織(せいしょく)
染め上がった糸を経糸と緯糸に分け、しぼが生まれるよう計算されたテンションで織り上げていきます。縞や格子といった伝統的な柄もこの段階で表現されます。 - 仕上げ
織り上がった布を湯に潜らせ、乾燥させることで自然な縮みが生じ、「しぼ」が浮かび上がります。このしぼこそが、阿波正藍しじら織の代名詞です。
完成したしじら織は、手に取るとふんわりと軽く、風を含んで揺れるようなやさしさを感じさせてくれます。
阿波正藍しじら織は、藍の深みと涼やかな「しぼ」を併せ持つ、徳島が誇る夏の織物です。偶然の雨から始まった発明が、今では世界に誇る伝統工芸に。藍と人の知恵が織りなすこの布は、現代の暮らしにも優しく寄り添います。