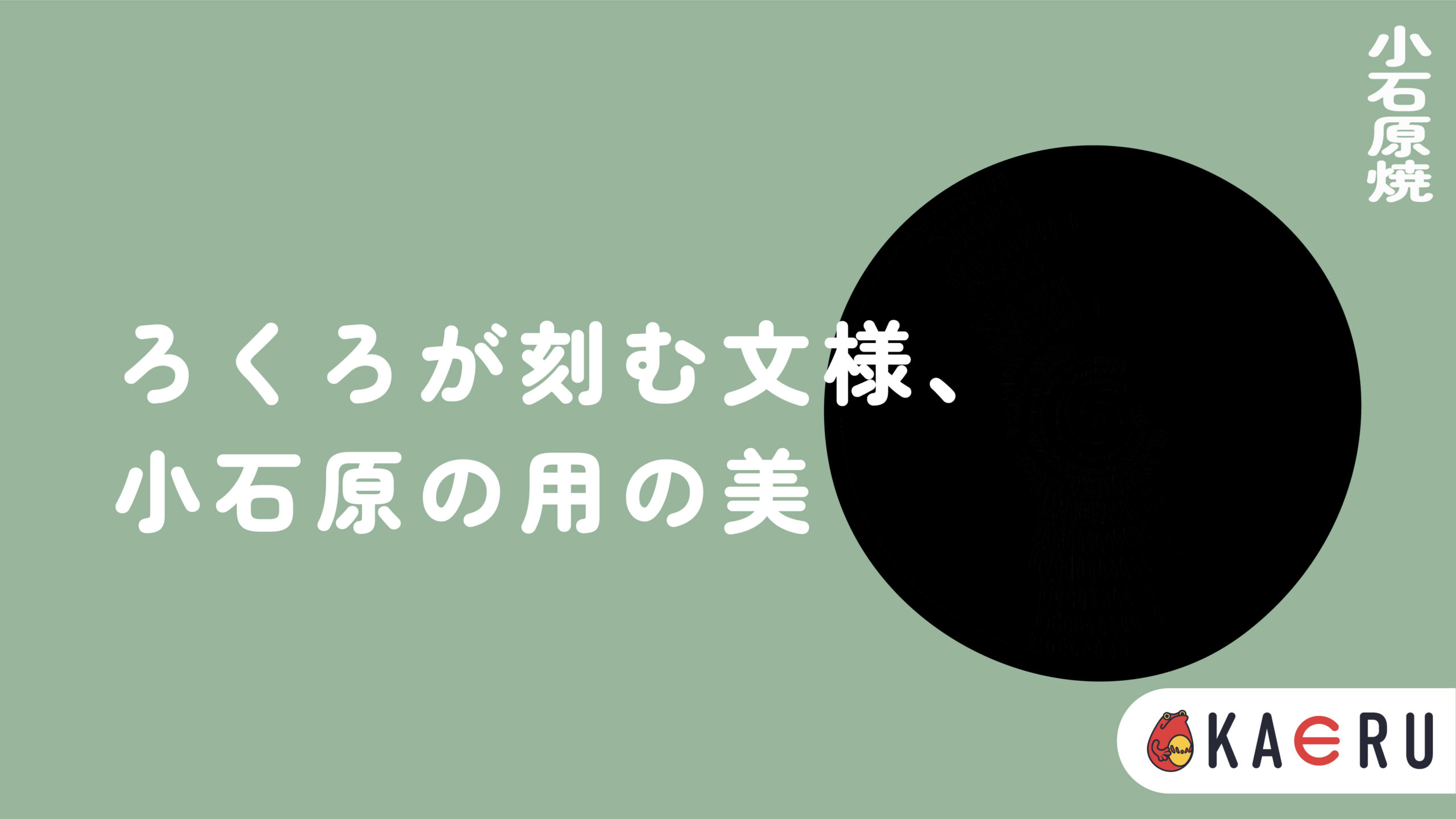小石原焼とは?

小石原焼(こいしわらやき)は、福岡県東峰村で生まれた日常使いの陶器です。江戸時代から約350年以上にわたり焼き続けられ、農家の生活道具としての役割を担ってきました。最大の特徴は、轆轤を回しながら道具で刻む独特の装飾にあります。「とびかんな」「刷毛目」「指がき」「櫛目」など、器にリズムを刻むように施された文様は、小石原焼独自の美意識と技術の象徴です。
実用性と素朴な美しさを兼ね備えた器は、1930年代以降の民芸運動で柳宗悦やバーナード・リーチらに評価され、全国にその名を広めました。現代でも、暮らしに寄り添う“用の美”を体現する焼物として、多くの人々に親しまれています。
| 品目名 | 小石原焼(こいしわらやき) |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 11(32)名 |
| その他の福岡県の伝統的工芸品 | 久留米絣、上野焼、博多織、八女福島仏壇、博多人形、八女提灯(全7品目) |
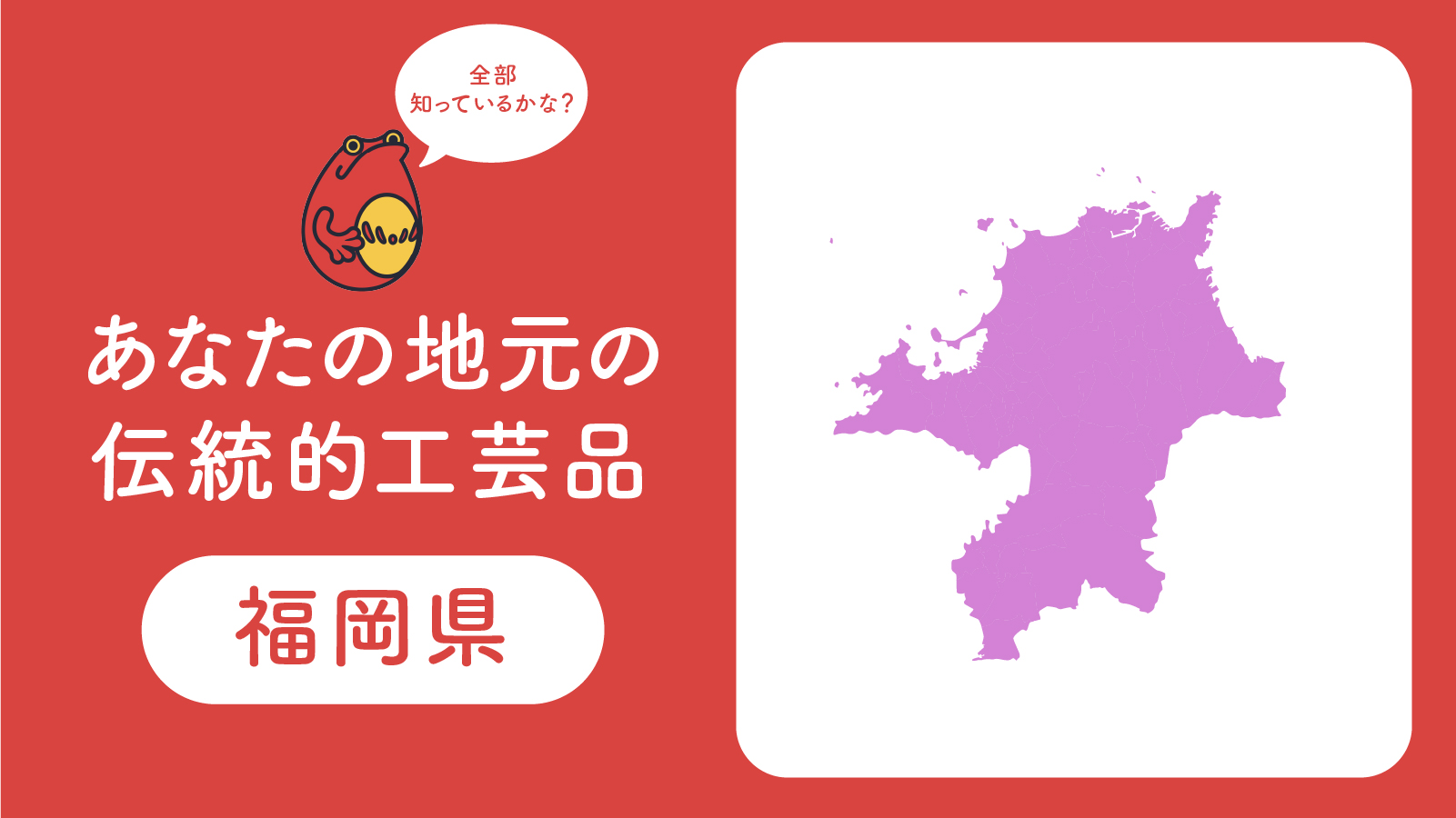
小石原焼の産地
赤土と民の知恵が育んだ、山里に息づく焼物の里

主要製造地域
小石原焼の産地である福岡県東峰村は、筑後川の上流域、耳納連山と英彦山地に挟まれた盆地状の地形にあります。この山間の集落では古くから焼物文化が根づき、地の利を活かした「暮らしの中の窯業」が育まれてきました。
地質的には、鉄分を多く含む良質な赤土が豊富に産出される地域で、器に温かみのある茶褐色の風合いを与えます。また、豊かな森林資源に恵まれていたため、薪窯に必要な木材も地元で調達することができました。さらに、雨量が多く清らかな水に恵まれていたことも、釉薬づくりや土練りの工程において重要な要素でした。
また、江戸時代初期に藩主黒田光之が伊万里から陶工を招き、技術移転が行われたことで、小石原の陶業が本格的に始動します。当時は農民が農閑期に陶器を焼いて自給し、余剰品を物々交換に用いる「民窯」の風習が一般的でした。
文化的にも、外界からの影響を受けにくい山村であったことから、生活に密着した実用品としての陶器が自然と求められ、質素ながらも堅牢で使いやすい器が作られるようになります。その姿勢は近代になっても変わらず、1930年代の民芸運動において「民衆の器」として再評価される背景にもなりました。
小石原焼の歴史
350年の暮らしとともに歩んだ、民陶の系譜
小石原焼は、江戸から現代に至るまで、民の手仕事として静かに、しかし確かに技を重ねてきました。
- 1682年(天和2年):福岡藩主・黒田光之が、肥前国伊万里の陶工を小石原に招く。技術導入により、小石原の民陶が始まる。
- 1700年代初頭:水甕・大甕・すり鉢など大型の生活用陶器の生産が本格化。農家の日常に欠かせない道具として定着。
- 1800年代初頭:轆轤装飾技法(とびかんな・指がきなど)が定着。各家ごとに独自の装飾様式が生まれる。
- 1873年(明治6年):ウィーン万国博覧会に出品され、素朴な民陶として国外でも注目を集める。
- 1931年(昭和6年):柳宗悦が民芸運動の中で小石原焼を紹介。「用の美」の代表例として国内で再評価。
- 1950年代(昭和30年前後):民芸ブームが全国に拡大。バーナード・リーチらの影響もあり、民芸品としての小石原焼が広く流通。
- 1975年(昭和50年):小石原焼が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:若手陶芸家の台頭とデザインの多様化が進む一方、「日々使う器」としての本質は変わらず継承されている。
小石原焼の特徴
器に刻まれるリズムと暮らしの美意識
小石原焼の最大の特徴は、器に施される装飾の“動き”にあります。轆轤の回転に合わせ、職人が櫛・刷毛・刃先・指などの道具を用いて、まるでリズムを刻むように文様を加えていくのです。とびかんなでは、一定のテンポで金属刃を当て、器の表面に連続的な削り跡を生み出します。素朴ながら非常に印象的な模様であり、使い続けるほどに陰影が増し、手に馴染む味わいが育ちます。
また「生がけ」と呼ばれる技法も特筆すべき点です。これは、素焼きを経ずに直接釉薬をかけて本焼きする方法で、ざらつきの残る素地の質感と、釉薬の透明感が相まって、唯一無二の肌触りを生み出します。
さらに「指がき」の装飾は、まさに手仕事の極み。土に直接指で描くため、同じ模様は二つとありません。このような個性ある表情が、量産品とは異なる「使い手との関係性」を生むのです。

小石原焼の材料と道具
土と道具が語る、手仕事の温もり
小石原焼の製作には、東峰村の豊かな自然から得られる土や釉薬、そして生活の中で工夫された道具が活用されます。職人が自らの手で生み出す道具も多く、生活と技の融合が見られます。
小石原焼の主な材料類
- 陶土(赤土系):地元の鉄分を含んだ粘土。焼成後の素朴な質感が特徴。
- 釉薬(わら灰釉・鉄釉など):柔らかな光沢と温かみのある色味を表現する。
小石原焼の主な道具類
- とびかんな:金属の刃を振動させて模様を刻む独自の道具。
- 刷毛・櫛:模様装飾用の筆道具。刷毛目・櫛目に用いられる。
- 指がき用道具:素手または木片で模様を描く。
- トンボ:器の直径を測るための木製道具(自作されることが多い)。
- 轆轤(ろくろ):手動式や電動式を使い分け、器の形を整える。
こうした道具と手の感覚を頼りに生み出される小石原焼は、機械量産とは異なる温もりと風合いを備えています。
小石原焼の製作工程
土から器へ、手と暮らしを結ぶものづくり
小石原焼の製作は、自然素材を扱う仕事ゆえに、その日の湿度や土の状態にまで気を配りながら行われます。
- 土づくり
地元の赤土を採取し、長期間寝かせてから、水簸や練りを行い粘りと可塑性を調整。 - 成形
轆轤を使い、器の形状や厚みを調整しながら丁寧に整える。 - 装飾
成形直後〜半乾燥の状態で、とびかんな・刷毛目・指がきなどを施す。 - 乾燥
じっくりと時間をかけて自然乾燥。季節や天候で工程が左右される。 - 施釉
素焼きを行わず、乾燥素地に直接釉薬をかける「生がけ」技法を採用。 - 本焼き
登り窯または電気窯で約1,200℃で焼成。炎の表情も仕上がりに影響を与える。
完成した器は、素朴ながらも力強く、暮らしの中で毎日使いたくなる質実な魅力にあふれています。
1975年に日本初の陶磁器指定を受け、以来高取焼の流れも汲む350年余の伝統を受け継ぐ小石原焼。1958年ブリュッセルの栄誉や、民陶祭・工芸館の存在などに裏付けされたストーリーと、飛び鉋・生がけなどの実直な技法が復合し、現代も“使うほどに愛着が増す器”として、多くの暮らしに寄り添い続けています。