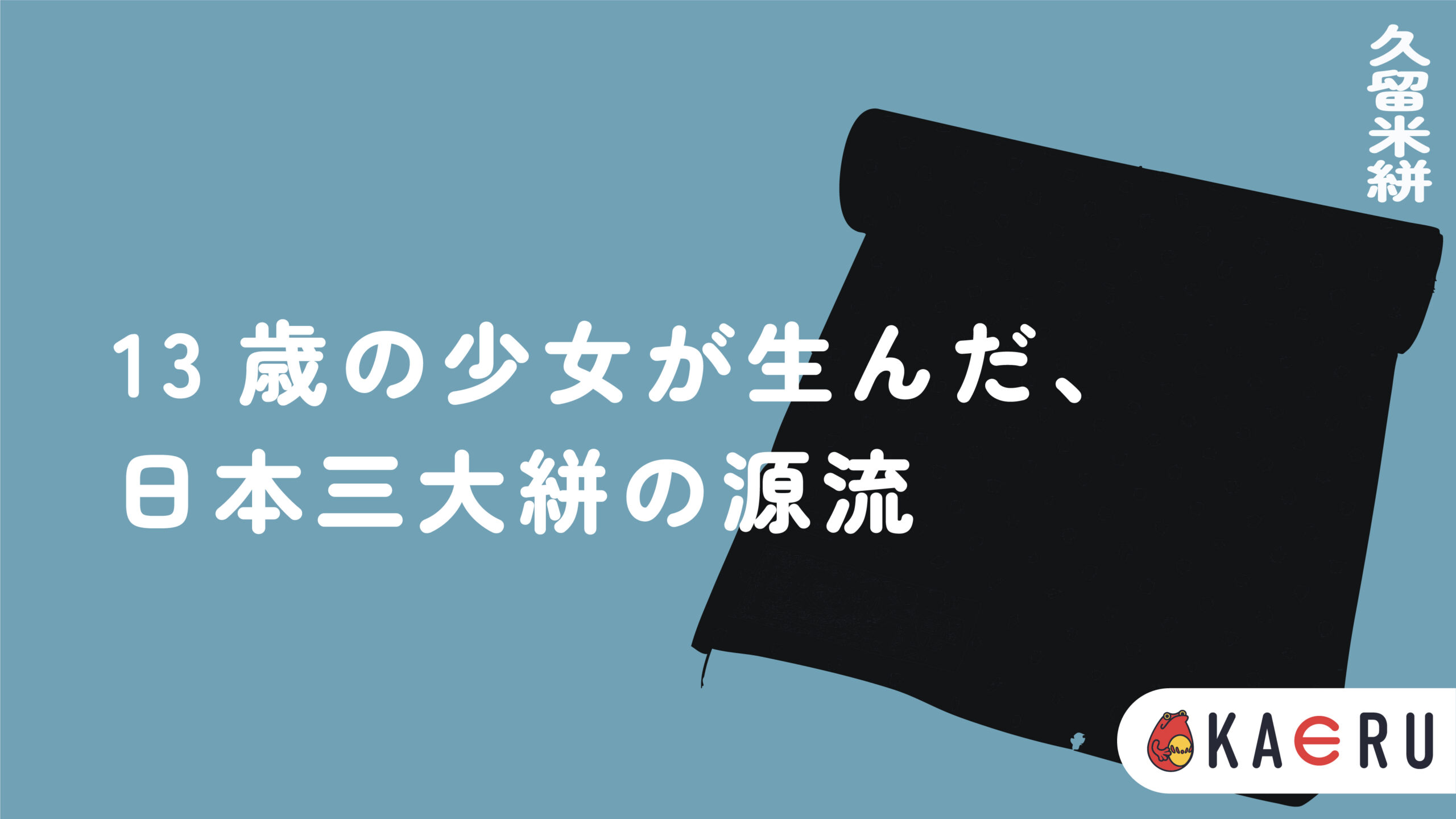久留米絣とは?

久留米絣(くるめかすり)は、福岡県久留米市を中心に作られる伝統的な木綿織物です。江戸時代後期、当時13歳だった井上伝という少女の発見をきっかけに誕生し、以降200年以上にわたり、庶民の暮らしを彩る日常着として親しまれてきました。
特徴的なのは、「くくり」と呼ばれる防染技法を用いて、糸に藍染めの濃淡を施し、織りの段階であえて“かすれ”のような模様を浮かび上がらせる点。こうして生まれる素朴な幾何文様や絵模様は、どこか懐かしく、現代の生活にもやさしくなじむテキスタイルです。
現在では、着物や作務衣にとどまらず、シャツやバッグ、インテリア雑貨など多様な製品にも展開され、伝統とモダンを融合させた工芸品として注目を集めています。
| 品目名 | 久留米絣(くるめかすり) |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(6)名 |
| その他の福岡県の伝統的工芸品 | 小石原焼、上野焼、博多織、八女福島仏壇、博多人形、八女提灯(全7品目) |
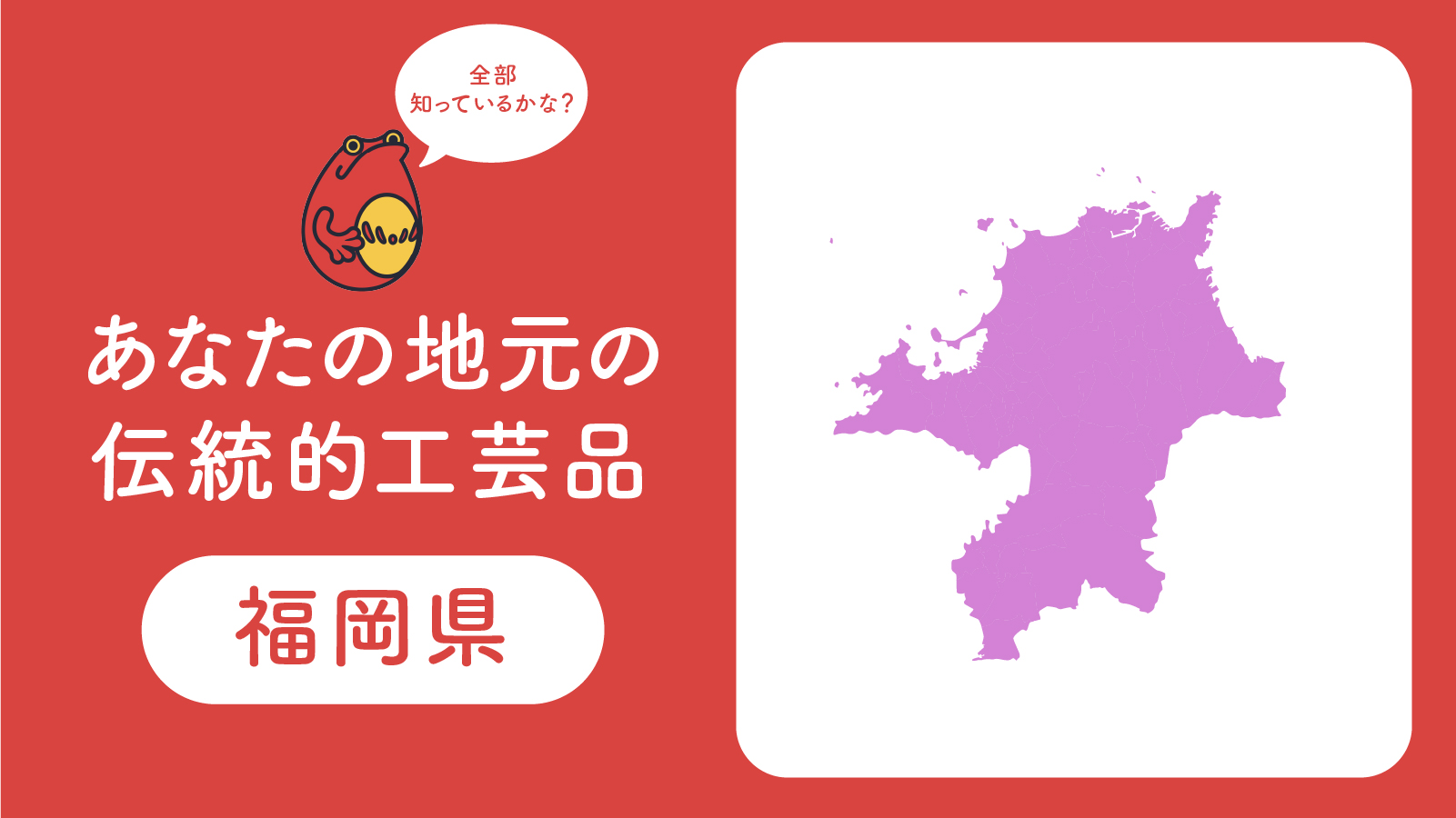
久留米絣の産地
筑後川の恵みと藍の伝統が育んだ、絣文化のふるさと

主要製造地域
久留米絣の産地である福岡県久留米市は、九州の北部、筑後川下流域に位置し、豊かな自然環境と水資源に恵まれています。この筑後川は、古くから肥沃な堆積平野を形成し、綿花の栽培に最適な土地を育んできました。江戸時代には藩の奨励政策により木綿の生産が活発になり、久留米は“筑後木綿”の名で知られる綿織物の一大産地へと成長していきます。
また、久留米は久留米藩の城下町として発展し、手工業や藍染文化が庶民生活に根付いていました。武士から町人に至るまで、木綿衣料が広く使われるようになったことで、庶民の衣生活に彩りを添える絣模様が受け入れられていったのです。
気候的にも久留米は温暖多湿で、綿の栽培や藍の発酵に適した環境が整っていました。天然藍の染色に欠かせないのは、適切な湿度と水質管理です。久留米には、藍建てに適した井戸水が豊富に存在し、現在でも“藍甕の管理は水が命”と語られるほど、藍染文化と土地の気候風土は密接な関係にあります。
このように、自然環境・歴史文化・気候条件の三拍子がそろった久留米は、絣文化を発展させるにふさわしい土壌を備えた場所でした。
久留米絣の歴史
13歳の少女が生んだ、日本三大絣の源流
久留米絣の歴史は、少女のひらめきと、それを支えた地域文化から始まります。
- 1802年(享和2年):13歳の少女・井上伝が、着古した藍染の着物に浮かぶ白い斑模様を見て、括り染めの発想を得る。
- 1808年(文化5年):試行錯誤の末に「本絣」の技法を確立し、藩に作品を献上。久留米藩が正式に保護を開始。
- 1810年代:伝の指導のもと、周囲の女性たちにも技法が広まり、産業化の基礎が築かれる。
- 1820年代〜30年代:技術の発展により、「緯絣」や「板絣」など新たな技法が誕生。柄の表現に多様性が生まれる。
- 1850年代(安政年間):九州一円に販路が広がり、「久留米絣」の名が定着。
- 1870年代後半(明治10年代):西洋の織機技術と融合しながらも、手括り・藍染による製法は維持される。
- 大正〜昭和初期:女性や子供の日常着としての需要が増大。柄のモダン化が進み、都市部でも愛用される。
- 1976年(昭和51年):久留米絣が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現在:若手職人やデザイナーによる再解釈が進み、衣類・雑貨・インテリアなどへの展開が拡大。
井上伝は後年、筑後絣技術の祖として藩から表彰され、現在もその業績は語り継がれています。
久留米絣の特徴
使うほどになじむ、暮らしに根ざした“かすれの美”
久留米絣の魅力は、なんといってもその“かすれ模様”にあります。意図的にかすれたように見えるこの柄は、絣糸の括りと藍染によって生み出される偶然と計算の結晶です。模様の位置は事前に図案と糸設計によって精密に決められていますが、織り上げたときに見える柄はすべてが少しずつ異なり、手仕事ならではの個性がにじみ出ます。
井上伝が最初に見出した斑模様のように、染まりきらない部分の白が藍の中でふわりと浮かび上がり、まるで絵画のぼかし技法のような効果をもたらします。こうした模様は、幾何学文様や草花、動物、抽象柄など多彩なデザインで展開されており、現代の感覚にもフィットする柔らかな印象を与えてくれます。
また、木綿素材のため夏はさらりと涼しく、冬は温かく、着るほどに肌になじみます。藍には防虫・消臭効果があり、洗うほど色に深みが増す“育つ布”としても評価されています。

久留米絣の材料と道具
自然素材が生む、やさしさと強さを織り込んで
久留米絣の製作には、地元で培われてきた自然素材と、伝統的な道具が用いられています。
久留米絣の主な材料類
- 木綿糸:通気性・吸湿性に優れた基本素材。久留米地域では綿花の自家栽培も行われていた。
- 粗苧(あらそう):麻の皮を割いて作る、括り用の天然繊維。
- すくも藍:藍の葉を発酵させて作る天然染料。色に深みと防虫性がある。
- 小麦粉糊:染めの際の糊付けに用いる、植物由来の素材。
久留米絣の主な道具類
- 括り縄:麻や綿でできた強靭な糸。模様の防染に使用。
- 絵紙(えがみ):図案用紙。括りの設計図となる。
- 高機(たかばた):立てて使う織機。絣模様を正確に再現するための重要な道具。
- 藍甕(あいがめ):藍染液を貯める容器。温度やpH管理が重要。
こうした素材と道具の調和が、やさしくも丈夫な久留米絣の風合いを支えています。
久留米絣の製作工程
すべての糸に意味を込める、30以上の職人仕事
久留米絣は、すべての模様が計算された糸の配置と染めによって生まれます。30以上におよぶ工程のなかでも、特に重要なのが“括り”と“藍染め”です。
- 図案作成
絵紙に模様を描き、経糸・緯糸の設計を行う。 - 絵糸書き
糸に図案通りの位置をマーキング。 - 括り
図案に沿って糸を麻ひもなどで強く縛り、防染部分を作る。 - 藍染め
括った糸を天然藍で繰り返し染め、色に深みを加える。 - 糸巻き・整経
括りを解き、経糸・緯糸として織機にセットする。 - 織り
高機を使って一糸ずつ織り上げ、模様を布として具現化する。 - 仕上げ・湯通し
織り上がった布を湯で洗い、余分な染料や糊を落とす。 - 検品・製品化
模様のズレや傷みを確認し、着物や雑貨として仕立てる。
各工程には熟練の手技が求められ、括りと染めの精度が絣の質を大きく左右します。
久留米絣は、江戸後期に少女の着想から生まれた、暮らしに寄り添う木綿の工芸です。藍と白のかすれ模様は手括りと藍染めの妙技によって生まれ、30以上の工程を経て布となります。使うほどになじみ、洗うほど深まる色味は、現代の生活にも静かに寄り添い続けています。