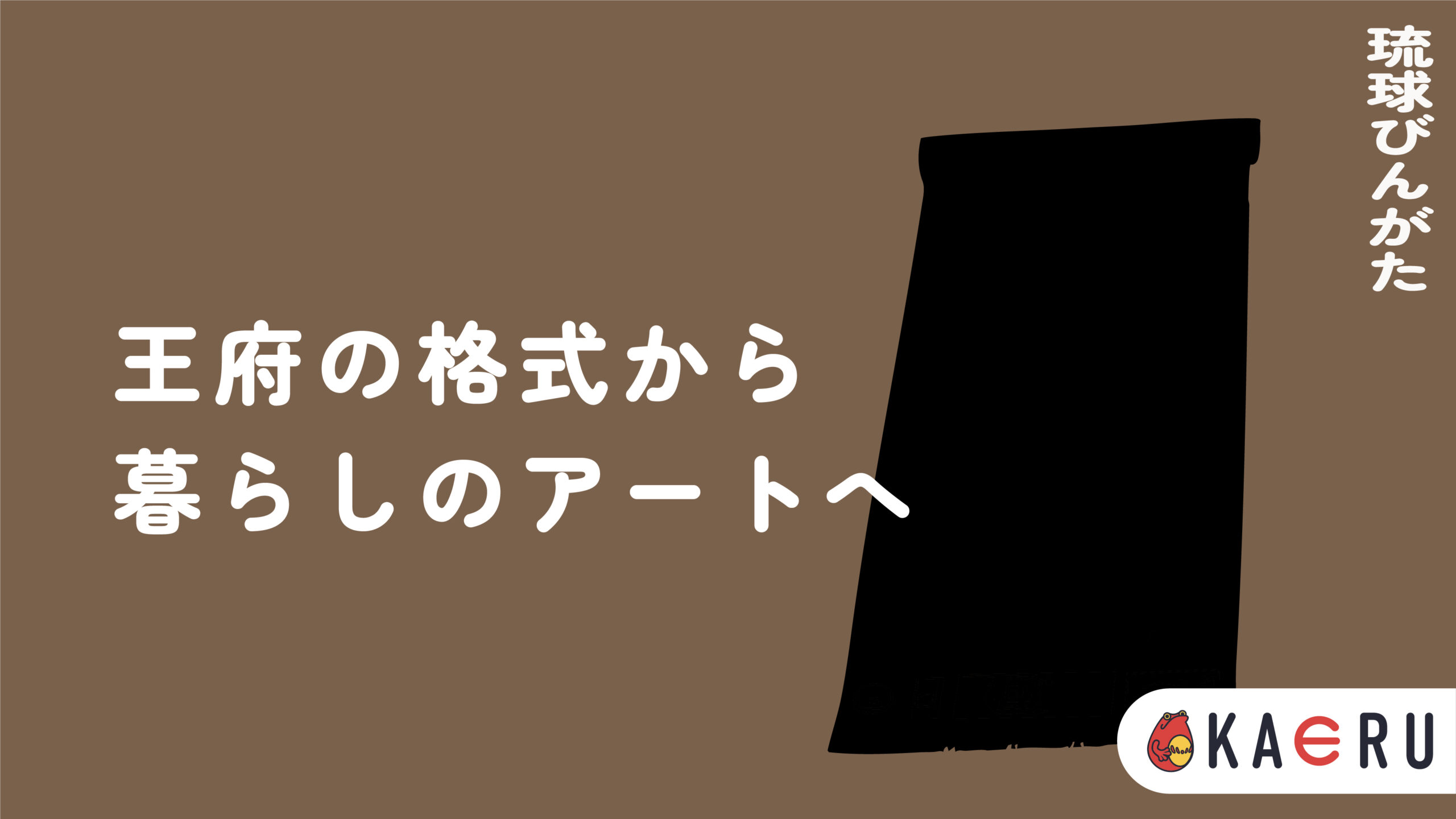琉球びんがたとは?
琉球びんがた(りゅうきゅうびんがた)は、沖縄県那覇市や浦添市などを中心に今も作られている伝統的な型染めの染色品です。色鮮やかな紅型(びんがた)と、藍一色で染め上げる藍型(えーがた)に大別され、花鳥風月をモチーフにした図柄と、立体感のある色彩表現が特徴です。
その起源は14〜15世紀にさかのぼり、中国やインド、東南アジア諸国との交易で得た染色技法をもとに発展しました。琉球王国の保護を受けながら洗練され、格式ある晴れ着や献上品としても重宝されてきた染め物文化は、現代ではインテリアや雑貨など新しい表現にも広がっています。
| 品目名 | 琉球びんがた(りゅうきゅうびんがた) |
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 分類 | 染色品 |
| 指定年月日 | 1984(昭和59)年5月31日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 6(14)名 |
| その他の沖縄県の伝統的工芸品 | 知花花織、久米島紬、宮古上布、読谷山花織、壺屋焼、琉球絣、琉球漆器、与那国織、八重山ミンサー、喜如嘉の芭蕉布、八重山上布、首里織、読谷山ミンサー、南風原花織、三線(全16品目) |

琉球びんがたの産地
那覇市や浦添市など、文化と自然が融合する染めの里

琉球びんがたは、主に沖縄県那覇市や浦添市などで作られています。この地域はかつて琉球王国の中枢として栄え、首里城を中心に染織や陶芸、漆芸などが集積していました。温暖多湿な気候と、南国らしい自然、独自の宗教観や生活文化が融合することで、びんがたならではの色彩と図柄が育まれています。
琉球びんがたの歴史
王朝文化の格式とアジア交易が育んだ色の芸術
琉球びんがたは、琉球王国時代の王朝文化とアジア諸国との活発な交易によって生まれ育まれた染色技術です。その発展の背景には、海洋国家としての琉球の立地と文化の受容性、そして王府の後援がありました。
- 飛鳥〜鎌倉時代:琉球に仏教や中国文化が伝わる。
- 14〜15世紀:琉球びんがたの起源。インド・ジャワの更紗、中国の印花布の技法が導入され、独自のびんがたが誕生。
- 16〜17世紀:琉球王国の保護を受け、貴族や王族の晴れ着・神事衣装として定着。
- 18世紀:藍型が登場。琉球藍を用いた藍染めが普及。
- 19世紀:中国・福建市場への輸出が盛んになり、東洋花布として珍重される。
- 20世紀前半:戦災により工房や型紙の多くが消失するが、職人たちの努力により復興。
- 1984年(昭和59年):琉球びんがたが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
琉球びんがたの特徴
顔料の鮮やかさと図柄の奥行きが織りなす、南国の詩情
琉球びんがたの特徴は、顔料を主に使うことで得られる発色の鮮やかさと、図柄に施される“隈取り(くまどり)”による奥行きのある立体感にあります。図案は南国の自然や動植物、空想的な文様が多く、四季の移ろいや神話的な世界観が表現されることもあります。
染色技法には、型紙を用いる「型付け(カタチキ)」と、筒状の袋から糊を絞って描く「筒描き(ツツビキ)」の2系統があり、前者では繊細な繰り返し模様、後者では自由でダイナミックな図柄が得意とされます。色は顔料を2度塗りし、さらに濃淡を加える“ぼかし”技法(隈取り)によって、絵画のような風合いが生まれます。

琉球びんがたの材料と道具
素材に宿る南国の知恵と職人の工夫
琉球びんがたの製作には、地元の気候風土に根ざした素材と、職人が自作する道具が欠かせません。下絵の彫刻には、豆腐を乾燥させたルクジューを敷いて行うなど、独特の工夫が随所に見られます。
琉球びんがたの主な材料類
- 顔料(鉱物系、植物系):紫外線に強く、鮮やかな発色が可能。
- 染料(琉球藍など):地染めに使用。
- 和紙(渋紙):型紙の素材として使用。
- 防染糊:もち米と糠を炊いて作られる。
- 生地(綿布、絹布、芭蕉布など):それぞれ異なる風合い。
琉球びんがたの主な道具類
- シーク(小刀):型彫りに用いる突彫用の道具。
- 刷毛・筆:顔料の色差しに使用。
- 糊袋:筒描き用の糊を絞り出す道具。
- ルクジュー:型彫り時の下敷き。
- 蒸し器:色定着のための蒸し工程に使用。
これらの道具や材料はすべて、職人の手によって手入れされ、環境や季節に応じて使い分けられます。
琉球びんがたの製作工程
ひとつの工房で完結する、丁寧な手仕事
琉球びんがたの製作は、すべての工程がひとつの工房で完結するのが特徴です。ここでは、型染めによる紅型の工程を紹介します。
- 型彫り(カタフイ)
下絵を渋紙に貼り、小刀(シーク)で突彫り。 - 型置き(カタチキ)
生地に型紙を置き、防染糊をヘラで塗布。 - 色差し(イルジヤシ)
糊のついていない部分に刷毛や筆で顔料を塗る。 - 隈取り(クマドウイ)
模様に濃淡をつけて立体感を表現。 - 糊伏せ
色を差した部分に糊を重ね、地染めの色が入らないように保護。 - 地染め
刷毛や染め液で全体に地色をつける。藍型は藍釜に浸して染める。 - 蒸し
高温で蒸して顔料や染料を定着させる。 - 水洗い・乾燥
余分な糊や顔料を水洗いし、天日で乾かして完成。
各工程は気候条件や素材によって調整され、経験に裏打ちされた職人技が求められます。
琉球びんがたは、琉球王国の交易と文化の交差点から生まれた、色彩と図案の芸術です。型紙を通した緻密な作業と、顔料の持つ鮮やかな発色、隈取りによる立体表現が織りなすその世界は、衣装や小物だけでなく、現代の暮らしにも自然に寄り添っています。