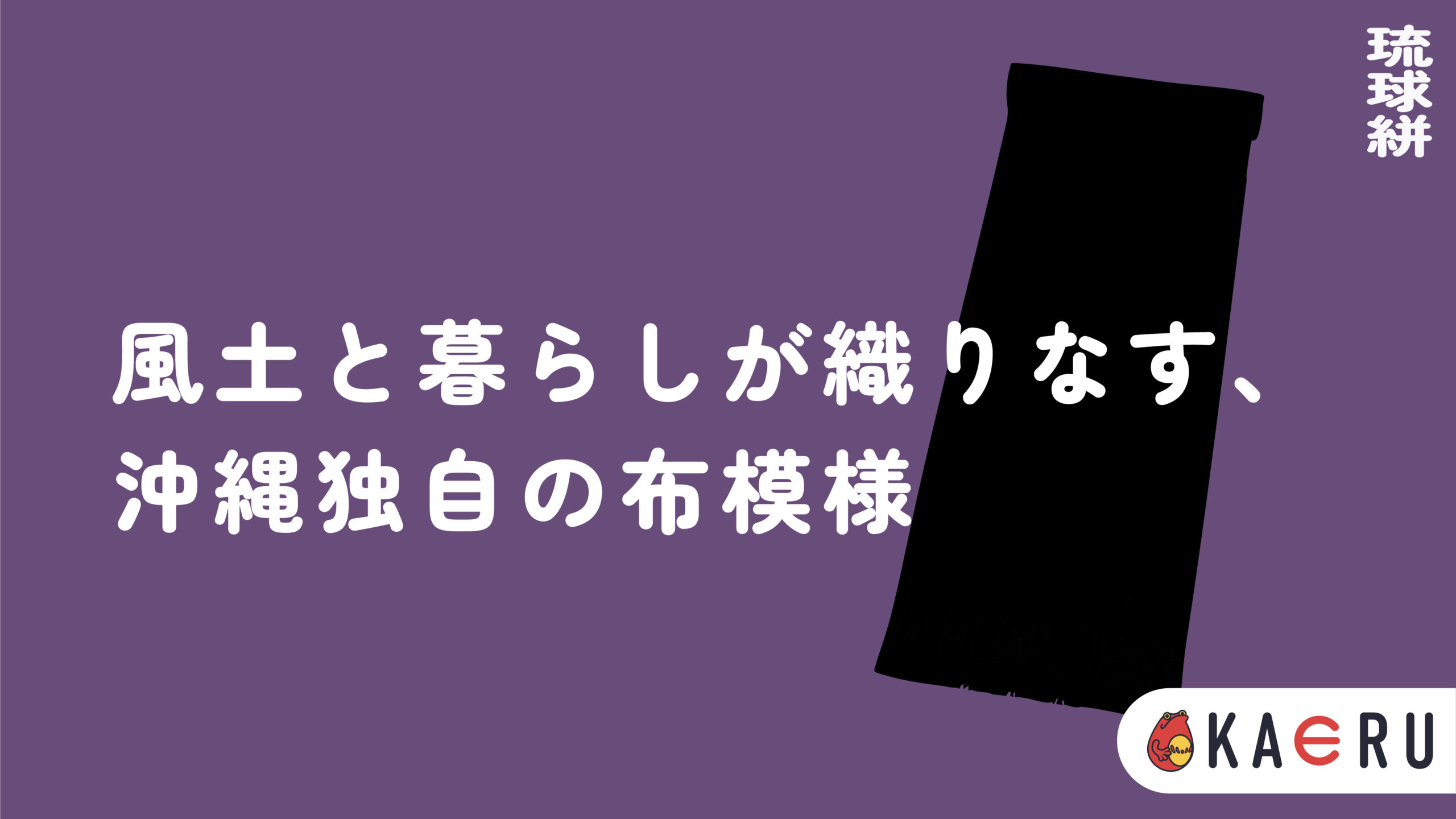琉球絣とは?
琉球絣(りゅうきゅうかすり)は、沖縄県島尻郡南風原町(はえばるちょう)を主産地とする、絣模様を特徴とした先染めの平織物です。絣とは、模様部分にあらかじめ染色した糸を織り込むことで、織り上げたときに絵や文様が浮かび上がる技法で、琉球絣では自然・動植物・生活道具などをモチーフにした約600種類以上の文様が伝承されています。藍色を基調とした落ち着いた色彩と、涼やかで素朴な風合いが特徴で、日常着や帯地などとして古くから親しまれてきました。
| 品目名 | 琉球絣(りゅうきゅうかすり) |
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1983(昭和58)年4月27日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 19(50)名 |
| その他の沖縄県の伝統的工芸品 | 知花花織、久米島紬、宮古上布、読谷山花織、壺屋焼、琉球漆器、与那国織、八重山ミンサー、喜如嘉の芭蕉布、八重山上布、首里織、読谷山ミンサー、琉球びんがた、南風原花織、三線(全16品目) |

琉球絣の産地
沖縄の風土と文化が息づく、南風原町を中心に

主要製造地域
琉球絣の主な産地は沖縄県南風原町。那覇市の南東に位置するこの地域は、かつて「絣の里」とも呼ばれ、戦前から絣の産地として知られてきました。戦後の復興期には、織物の再興を目指して「琉球絣事業協同組合」が発足。今日では複数の工房や織元が集まり、職人の手仕事によって伝統が継承されています。
また、体験施設や教育活動を通じて後継者育成や観光活用も進んでおり、地域に根ざした産業として重要な役割を果たしています。
琉球絣の歴史
王朝文化の格式から、庶民の暮らしへと広がった布
琉球絣の起源は、15世紀ごろの琉球王朝時代にさかのぼるとされます。東南アジアをはじめとする南方諸国との交易を通じて、絣の技術が琉球に伝来。首里を中心とする王族や士族の衣装として取り入れられた後、やがて農村部にも普及し、庶民の衣類として広く使われるようになりました。
- 15世紀:東南アジアなどとの交易により、絣の技術が琉球に伝来。
- 17世紀:王府による産業振興政策のもと、織物生産が制度化される。
- 19世紀:模様の種類が増え、各地に地域色のある琉球絣が定着。
- 1930年代:南風原町での生産が活性化し、沖縄を代表する織物となる。
- 戦後(1950年代以降):南風原を中心に組合が結成され、技術保存と普及が進む。
- 1983年(昭和58年):琉球絣が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
琉球絣の特徴
日々の営みが文様に宿る、実用と美を兼ねた織物
琉球絣の大きな魅力は、模様に込められた物語と、日常の中での使いやすさにあります。模様は一つひとつに意味があり、「子孫繁栄」や「無病息災」など、暮らしの願いや祈りが込められています。代表的な文様には、「トゥイグヮー(鳥)」「カタカシー(風車)」「クヮンクヮン(豆)」など、素朴で親しみやすいモチーフが多く見られます。
使用される糸は綿や絹で、染料には藍や福木、車輪梅(シャリンバイ)などの天然染料も用いられます。織り上がった布は軽く、さらりとした手ざわりで、沖縄の高温多湿な気候にも適応。衣料品としての実用性と、美術工芸としての装飾性を兼ね備えています。

琉球絣の材料と道具
風土が育む天然素材と、手織り文化を支える道具
琉球絣の製作には、自然と共生する沖縄ならではの素材と、伝統的な織りの道具が使われています。とくに染めに使用される植物染料は、琉球王朝時代から続く自然由来の色彩文化の一端を担っています。
琉球絣の主な材料類
- 綿糸:主に経糸として使われ、吸湿性と耐久性に優れる。
- 絹糸:緯糸に使われることもあり、しなやかな風合いを出す。
- 藍、福木、車輪梅などの天然染料:自然な色合いと耐光性を併せ持つ。
琉球絣の主な道具類
- 板締め道具(絣括り板など):模様部分を括って防染処理を行う。
- 糸繰り機:染色前に糸を整理・準備する。
- 高機(たかばた):足踏み式の立機で、琉球絣特有の織りに使われる。
- 綛枠・管巻き:糸の管理や準備作業に使用。
それぞれの素材や道具には長年の工夫と職人の知恵が凝縮されており、微細な調整が織物の完成度を左右します。
琉球絣の製作工程
括って染めて、精緻に織る。熟練の技が生む模様の世界
琉球絣は、染める前の糸にあらかじめ模様を施す「先染め」の絣技法が用いられます。工程はすべて手作業で進められ、1反の布を仕上げるのに数週間から数か月を要することもあります。
- 図案設計
文様や配色の設計図を作成する。 - 絣括り
模様に応じて糸を括り、防染加工を施す。 - 染色
括った糸を天然染料などで染め分ける。 - 解き
括り糸を外し、模様部分を露出。 - 整経
染め上がった糸を織機に整える。 - 織り
模様の位置を正確に合わせながら手織りで仕上げる。 - 水洗い・乾燥・仕上げ
完成布を洗い、形を整えて製品化。
模様がにじまず美しく出るようにするためには、各工程で職人の緻密な調整が必要不可欠です。とくに模様がぴたりと一致するように糸を合わせていく「絣合わせ」の工程は、長年の経験が求められる高度な技術とされています。
琉球絣は、沖縄の自然・文化・暮らしが織り込まれた、唯一無二の絣織物です。素朴ながらも深い意味をもつ文様と、涼やかな風合いは、現代のライフスタイルにも寄り添います。衣料や帯、小物だけでなく、インテリアやアート作品としても注目が高まっており、琉球の美意識を今に伝える“生きた伝統”として、多くの人々を魅了し続けています。