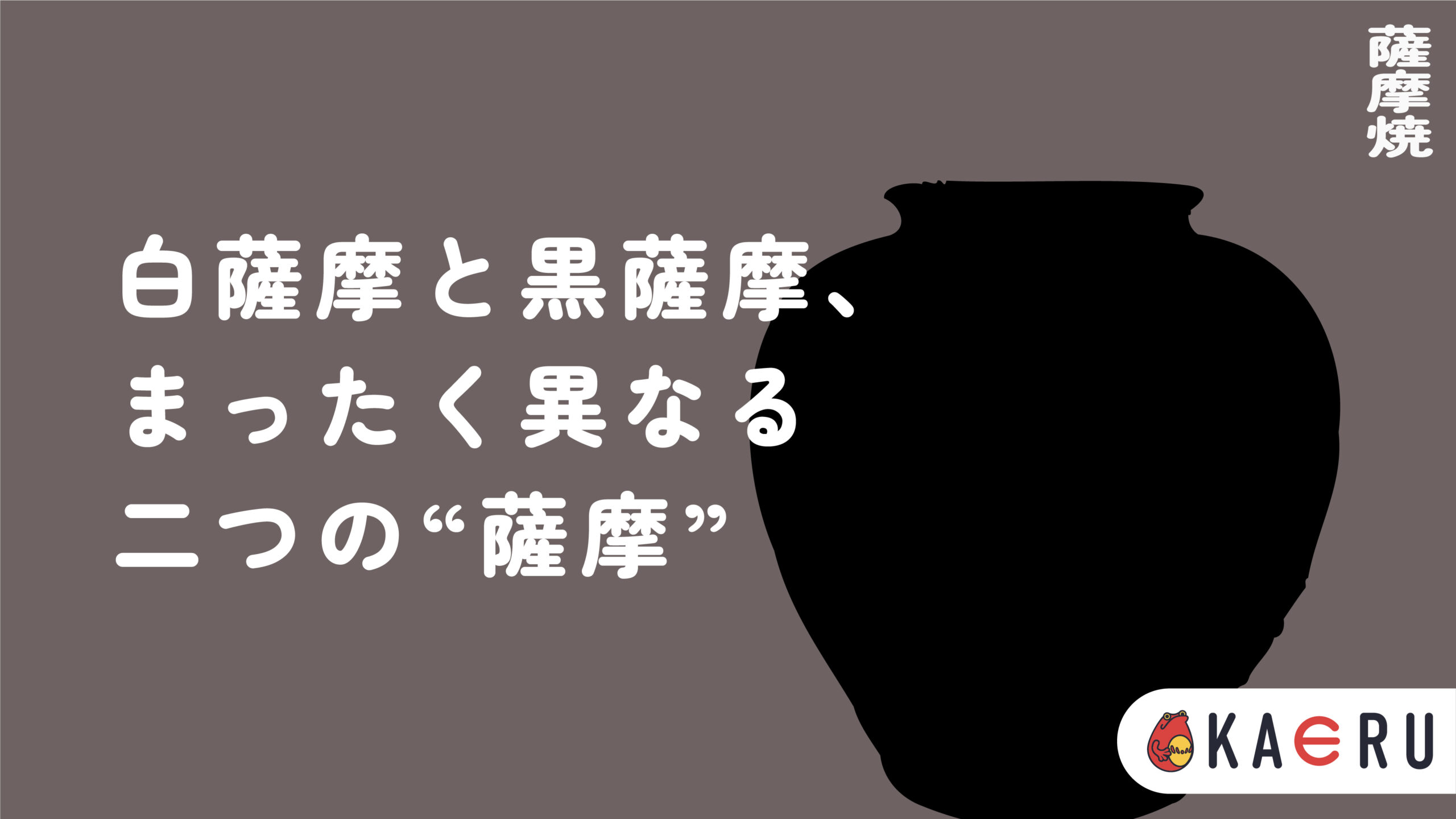薩摩焼とは?

薩摩焼(さつまやき)は、鹿児島県を中心に製作される伝統的な陶磁器です。起源は16世紀末、薩摩藩主・島津義弘が朝鮮から陶工を伴って帰国したことにさかのぼります。
その後、地元の土と火、そして陶工たちの技が融合し、「白薩摩」と「黒薩摩」という異なる美意識を併せ持つ独自のやきもの文化が築かれました。白薩摩は細やかな貫入と華やかな装飾が特徴で鑑賞用の上等品として珍重され、黒薩摩は素朴で力強い日用の陶器として人々の暮らしに根づきました。
現在も、伝統を守りながら現代的な感性と融合した作品が多く生み出されており、日本国内外で高い評価を受けています。
| 品目名 | 薩摩焼(さつまやき) |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 2002(平成14)年1月30日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(13)名 |
| その他の鹿児島県の伝統的工芸品 | 本場大島紬、川辺仏壇(全3品目) |

薩摩焼の産地
火山の恵みと異文化の融合が生んだ陶の里

主要製造地域
薩摩焼の主な産地は、鹿児島県の鹿児島市、日置市、指宿市など広範囲にわたります。中でも、日置市美山町(旧苗代川村)は「薩摩焼発祥の地」として知られ、朝鮮から連れてこられた陶工たちが根を下ろした場所です。文禄・慶長の役で島津義弘が朝鮮から陶工を連れて帰った1598年以降、藩が彼らを保護し、御用窯を設けて育成したことが大きな契機となりました。その後、美山や竪野、龍門司などに窯業地が形成され、各地で技法が発展・分化していきました。
薩摩藩が白薩摩を外交・贈答用の工芸品として重視したことで、洗練された美術陶器の文化が生まれました。また庶民の間では、焼酎文化や農漁業の生活に根ざした黒薩摩が欠かせない日用品として受け入れられました。
また、鹿児島は活火山・桜島を擁する火山地帯であり、鉄分や火山灰を含む多種の粘土資源が豊富です。また高温の薪窯焼成に適した地形や、近くの山林から薪となる木材も入手しやすく、登り窯を維持する環境が整っていました。
このように、地理・歴史・文化が重なり合って、薩摩焼という多彩な陶芸文化が育まれてきたのです。
薩摩焼の歴史
異文化の融合から生まれた薩摩の焼物文化
薩摩焼は朝鮮半島からの陶工たちの技術と、薩摩の土・火・美意識とが融合することで誕生した、日本でも類を見ない独自の陶磁器文化です。
- 1598年(慶長3年):島津義弘が朝鮮半島から約80人の陶工を伴い帰国。薩摩各地に移住させ、窯業を興す。
- 1600年代初頭:苗代川(現・日置市美山町)に御用窯が築かれ、白薩摩の生産が始まる。藩主への献上品や贈答用として扱われる。
- 1615年(元和元年):薩摩藩が「唐人町(陶工町)」を整備し、陶工の保護政策を本格化。
- 1680年代:竪野・龍門司など他地域でも窯が築かれ、黒薩摩を中心とした民窯文化が広がる。
- 1700年代中頃:白薩摩に色絵・金彩の装飾技法が導入され、美術陶器としての完成度が高まる。
- 1854年(安政元年):日米和親条約締結により、薩摩焼が海外へ紹介され始める。
- 1867年(慶応3年):パリ万博に出品され、白薩摩が“SATSUMA”ブランドとしてヨーロッパで脚光を浴びる。
- 1873年(明治6年):ウィーン万博でも高評価。宮廷文化の愛玩品として人気を集める。
- 大正〜昭和初期:一部輸出向け産地の衰退とともに、黒薩摩の見直しが始まる。
- 2002年(平成14年):薩摩焼が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:作家系陶芸家による再興が進み、現代アートや食器としても注目。
現代においても、白薩摩・黒薩摩の両系統が継承され、陶芸家たちの創作により新たな展開を見せています。
薩摩焼の特徴
気品と温もりを併せ持つ、二つの“薩摩”
薩摩焼の魅力は、白薩摩と黒薩摩というまったく異なる性格を持つ2つのやきものが同時に存在している点にあります。白薩摩は、滑らかで白く上品な素地に細かな貫入が入り、金彩や赤絵で華やかに装飾された作品が多く見られます。これらは鑑賞用として制作されたもので、「見るためのやきもの」としての性格が色濃く、明治期には欧米の王侯貴族の間でも人気を博しました。中には「1つの器に半年かけて絵付けをする」と言われるほど精密な作品も存在します。
一方の黒薩摩は、赤褐色〜黒色に発色する鉄分の多い陶土を使い、厚手で素朴な風合いが魅力です。焼酎甕や茶碗など、日常使いに耐える丈夫さと温かみがあり、焼成中に偶然できる釉薬の流れや火のあたりによる「窯変(ようへん)」が、世界に一つだけの表情を生み出します。
白薩摩は“薩摩”ブランドとして世界に広まりましたが、実際には鑑賞用で生産数が少なく、黒薩摩の方が薩摩の人々の暮らしを支えてきた「本来の薩摩焼」とも言える存在なのです。
このように、用途や表現の異なる2つの薩摩焼は、それぞれの美意識を体現しながら共存し、薩摩という土地の多様性を象徴する存在となっています。

薩摩焼の材料と道具
薩摩の土と釉薬が育む、色と表情の奥深さ
薩摩焼の製作には、火山灰や粘土層から採れる陶土と、自然由来の釉薬が用いられます。素材の選定から調合まで、細やかな感覚が求められます。
薩摩焼の主な材料類
- 薩摩陶土(白土):貝殻質を含む細かな粒子の粘土。白薩摩に使用。
- 薩摩陶土(赤土・黒土):鉄分を多く含み、焼成で黒く発色。黒薩摩に使用。
- 長石・木灰・わら灰:釉薬の原料。
- 金・赤・青・緑などの顔料:上絵付けに使用。
薩摩焼の主な道具類
- 蹄(ひづめ):成形時に用いる竹製の道具。
- ろくろ:電動・手動いずれも使用。
- 刷毛・筆:釉薬や絵付けに使用。
- 彫刻刀:装飾や浮彫細工に使用。
- 登り窯・電気窯:焼成に使用される窯。
白と黒、それぞれの薩摩焼に応じて材料や焼成法が変わる点も、深い専門性と技術の証といえるでしょう。
薩摩焼の製作工程
窯の炎が仕上げる、白と黒のやきもの物語
薩摩焼の製作は、採土から焼成まで、精緻な工程を経て一つひとつ丁寧に仕上げられます。
- 採土・精製
地元の陶土を採取し、不純物を取り除いて寝かせる。 - 成形
轆轤や手びねりで器の形を作る。黒薩摩では大物が多く、力強い成形が求められる。 - 乾燥
形を崩さぬよう慎重に乾燥させる。 - 素焼き
700〜800度程度で一度焼くことで強度を持たせる。 - 絵付け・釉掛け
白薩摩では色絵・金彩を加え、黒薩摩では鉄釉などを施す。 - 本焼き
登り窯や電気窯で1200度前後の高温で焼成。焼成中の火のあたり方で風合いが変化。 - 上絵焼き(白薩摩のみ)
本焼き後に金彩や赤絵を加えて再焼成する。
こうして完成した薩摩焼は、薩摩の自然と歴史、そして職人の感性が結晶した、世界に誇る陶磁器として今日も愛され続けています。
薩摩焼は、異文化の出会いと薩摩の風土が織りなした日本有数の陶磁器文化です。白薩摩の繊細な美、黒薩摩の素朴な力強さは、それぞれ異なる価値観を映し出しながら共存しています。400年にわたり受け継がれるその技と心は、今なお薩摩の地で静かに燃え続けています。