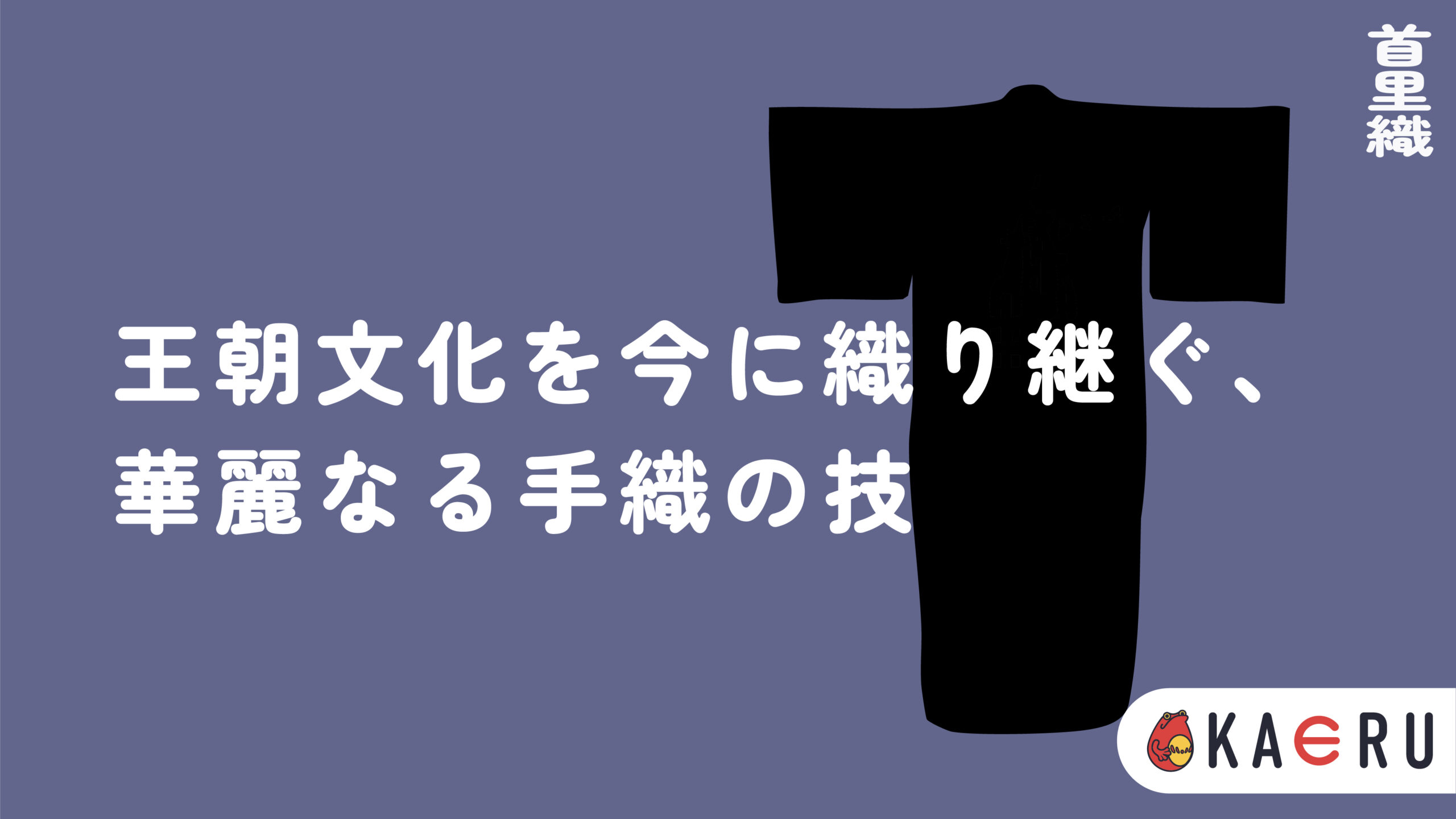首里織とは?
首里織(しゅりおり)は、沖縄県那覇市首里地域を中心に受け継がれる、格調高く洗練された風合いを持つ伝統織物です。琉球王朝時代、王族や士族の正装として重用された織物であり、その技法は多岐にわたり、「花織(はなおり)」「道屯織(どうとんおり)」「絽織(ろおり)」「紋織(もんおり)」「経錦(たてにしき)」など、複数の織技を総称して首里織と呼びます。色彩は気品ある彩りが特徴で、繊細な文様表現と上質な光沢感が見る者を惹きつけます。
現在もすべて手織りで製作され、衣料や帯としてだけでなく、美術工芸としても評価されています。
| 品目名 | 首里織(しゅりおり) |
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1983(昭和58)年4月27日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(9)名 |
| その他の沖縄県の伝統的工芸品 | 知花花織、久米島紬、宮古上布、読谷山花織、壺屋焼、琉球絣、琉球漆器、与那国織、八重山ミンサー、喜如嘉の芭蕉布、八重山上布、読谷山ミンサー、琉球びんがた、南風原花織、三線(全16品目) |

首里織の産地
王都・首里の地に息づく、織の伝統

首里織の主な産地は沖縄県那覇市首里地域です。かつて琉球王朝の都が置かれたこの地には、王府直轄の織場(おりば)である「御織殿(うおりどの)」が設けられ、王族・士族の衣装を専門に製作していました。現在も首里の町には伝統織物の工房が点在し、王朝文化の面影を残す街並みとともに、職人たちが手仕事を受け継いでいます。地域内では教育・継承活動も盛んで、那覇市内の高校や専修学校で織物技術を学ぶ場も提供されています。
首里織の歴史
王朝のための織物から、現代の工芸へ
首里織の起源は明確ではないものの、14〜15世紀にはすでに王府の庇護のもとで発展を遂げていたとされています。周辺諸国との交易により中国・朝鮮・東南アジアからも織技術が流入し、それらを取り入れながら琉球独自の美意識が育まれていきました。
- 14〜15世紀:王府直属の「御織殿」で織物制作が制度化される。
- 16〜17世紀:冊封使への献上品や王族・士族の礼装として、格式の高い織物として定着。
- 18世紀以降:花織・道屯織・絽織など、多様な織技法が発展。
- 明治時代以降:琉球王国の消滅とともに織物業も一時衰退。
- 戦後:保存活動とともに織物文化の復興が進み、工房が再建される。
- 1983年(昭和58年):首里織が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
首里織の特徴
気品と多彩な技をあわせもつ、沖縄の織の粋
首里織の大きな魅力は、その織技法の多様さと文様の繊細さにあります。代表的な技法である「花織」では、浮き織によって立体的な文様が表現され、花々や幾何学模様が織り込まれます。「道屯織」は経糸と緯糸の組み合わせで複雑な文様を出す技法で、「絽織」は透け感を出すことで涼やかさを演出します。
色彩は赤・黄・藍・緑などの鮮やかさと落ち着きが両立し、王朝文化にふさわしい格調の高さを感じさせます。全体として織りの精密さと文様の上品さが調和しており、帯や着物地としてはもちろん、現代では装飾品やアート作品としても高く評価されています。近年ではファッションブランドとのコラボレーションや、インテリアテキスタイルへの展開も見られ、首里織の魅力はさらに多様な広がりを見せています。

首里織の材料と道具
上質な素材と、洗練された技術を支える道具
首里織に使われる素材と道具には、繊細な織表現を支えるための工夫が凝らされています。使用される糸は高品質の絹糸が中心で、染料には植物由来の自然染料が伝統的に使われてきました。
首里織の主な材料類
- 絹糸:上質な光沢と手ざわりを持つ。経糸・緯糸ともに使用。
- 植物染料(フクギ、アイ、車輪梅など):彩度と深みのある色合いを生む。
- 化学染料:安定した発色や再現性を必要とする場合に使用されることもある。
首里織の主な道具類
- 高機(たかばた):縦方向に糸を張る足踏み式の織機。
- 綛枠・管巻き:糸の準備や管理に使用。
- 杼(ひ):緯糸を通すための道具。
- 仕上げ用の湯のし機:織り上がった布を整える。
素材と道具の選定から織りの工程まで、細部にわたる職人の気配りが、首里織の優雅さと完成度の高さを支えています。
首里織の製作工程
技法ごとに異なる織りの美を表現する丁寧な手作業
首里織は多様な技法の集合体であるため、工程も技法ごとに異なりますが、以下は代表的な「花織」の製作手順に基づく一般的な流れです。
- 図案設計
織り上がりを想定して文様や配色を設計する。 - 糸染め
植物染料などで経糸・緯糸を染色。 - 整経
染め上がった経糸を必要な長さと本数に整える。 - 機巻き
経糸を織機にセットし、張力を調整。 - 織り
花織や道屯織などの技法で文様を手織りする。 - 検品・仕上げ
布の表面を確認し、湯のしで仕上げる。
緻密な図案設計と色合わせが作品の印象を左右するため、職人は織りの前段階から細心の注意を払います。織りの工程では技法ごとの異なる操作が求められ、高い技術と集中力が不可欠です。
首里織は、琉球王朝の格式と美意識を今に伝える織物文化の結晶です。多彩な技法と気品ある色彩、緻密な織りが生み出すその魅力は、見る者の心を引き込む力を持っています。現代では伝統衣装にとどまらず、インテリアや工芸作品、ファッション分野などでも活用され、王都・首里の誇りとして日本全国、そして世界へと発信されています。